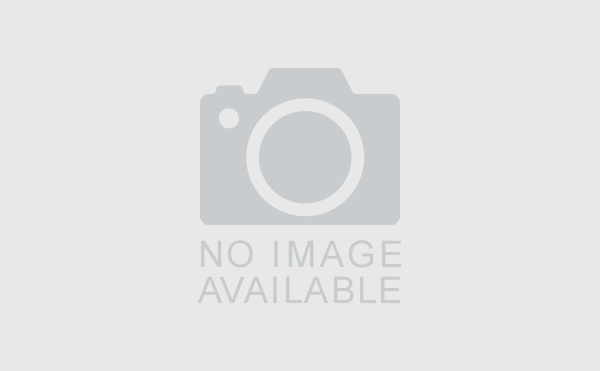短歌同好会:9月歌会の様子をご紹介させて頂きます。
「短歌同好会」は、コロナ禍の最中においても、オンライン(Zoom)で毎月の歌会を実施していましたが、この4月からは日比谷ビル喜楽会室にてリアルの歌会を再開しています。
9月9日(金)の日比谷短歌会の歌会は、初めて参加のお一人を加えて8名の会となりました。(お一人だけご都合が悪く欠席されました。)

毎月の歌会は前月末の締切りまでに、講師の石田信二先生に、所属会員(歌会欠席者含む)がそれぞれ2首を提出し、歌会当日ではその1首ごとに、詠み人本人を除く参加メンバーから当該短歌についての感想や添削のコメントが求められます。そして、最後に石田先生が添削をした歌が披露されるという形式で進められます。

9月の歌会では、接続詞の「て」を使わない、ということを強く教わりました。
例を挙げますと、
(原歌)盆過ぎて懸命に鳴く蝉の声 夏の終わりを告げているよう
(添削)盆を過ぎ懸命に鳴くアブラゼミ 夏の終わりを告げているがに
「盆過ぎて」は、「盆を過ぎ」として「て」は使わない。「て」を使うと短歌では説明的になるといわれているためです。(原歌は持丸光次郎さんの歌でした。)
それでは、持丸さん以外の方の歌を、石田先生に添削いただいたものでご紹介しましょう。
・保母さんは体を張って身を呈し園児を事故から守り助ける(梶ます子さん)
・名古屋場所 唇噛んでひきあげる力士のこぶし震え止まらず(近藤君子さん)
・熟桃の皮引く指に溢れくる滴も香をもいとしみ食す(原歌のまま、亀井枝美さん)
・戻り梅雨に蝉も出番を逃したか 遠くで鳴いてる蝉にエールを(佐藤悟さん)
・いつからか尋ねる人のない我が家 バカラグラスが静かに鎮座(原歌のまま、大杉富士子さん)
・今年またシルバー川柳読み終えて ガッテンするも胸沈む吾(続谷恵二)
・ときめきは他人(ひと)のものかと想うわれ 今は昔と思い出すなり(奥津登喜子さん)
・「美人には他人(ひと)の痛みが分からない」 妻はまあまあ分かると思う(石田信二先生)

如何でしょうか?短歌を詠むのは、難しくもあり、易しくもあります。これらのメンバーとご一緒に短歌を楽しんでみませんか。興味のある方は世話役の続谷(090-6007-9930)までご連絡願います。
【 短歌同好会世話役 続谷恵二 記 】
Views: 8