小袖会:10月10日(火)「大松染工場」見学に行って来ました。
10月10日(火)12時30分に東武線の「曳舟駅」の前にある「イトーヨーカドー」の1階に今回の参加者15名の内の9名が集合し、徒歩約12分で「大松染工場」に着きました。他の6名の方は2台の車で既に工場に直接着かれていました。

小袖会として記念となる第1回「きもの産地見学会」なので同工場の展示施設棟(ミニ博物館と工房ショップ)の前で皆さんの集合写真を撮らせて頂きました。

まず13時より、参加者全員を対象に、経済産業省の伝統工芸士の資格を持たれる当工場の2代目の中條隆一氏と3代目の中條康隆氏から「江戸小紋とはどのようなものか」及び「江戸小紋と江戸更紗の違い」について、歴史及び製法及び現代における技術的進化について、ビデオも使いながら詳しくご説明頂きました。
質問時間も取って頂き、ご丁寧な回答を頂きました。13時50分になったところで、一般見学コース(無料)の8名と染体験コース(有料@5000円)の7名に分かれました。


一般見学コースの参加者は引き続き展示施設棟にて、2代目と3代目の奥様から極細の紋様に切り抜かれた型紙や色糊を浸けるヘラ等の道具の実物について説明を受けた後に2階の着物の展示コーナーと1階のショッピングコーナーにて各商品の説明を受けました。
皆さん着物だけでなくシャツやブラウスや小物等がデパート等に比べてかなりお安く販売されているのにびっくりされており、購入された方も数名いらっしゃいました。
一般見学コースとしては14時30分に終了しました。車組(1台)と「曳舟駅」までの徒歩組に分かれる為、工場にて解散しました。

染体験コースの参加者は、工場棟の2階に移動し、まず最初に型紙(縦約30㎝×横約38㎝)を布地代わりの白い紙に乗せ、その上に染料が混ざった糊を置いてヘラでのばす「型付け」の練習を3代目と4名の熟練工員の方々より細かくご指導を受けました。
特に型紙の星(型紙を合わせるための目印となる1ミリに満たない穴)を合わせながら、「型付け」作業を4回繰り返しましたが、柄がズレたり、色ムラがあったり、その困難さを身をもって体験出来ました。


練習が終わるといよいよ自分だけのオリジナルの「ランチョンマット」の制作に取組みました。各自が選んだ型紙と布地を使って金色の染料が混ざった糊の「型付け」をしました。1回だけの「型付け」なので、紋様がズレる心配はありませんでしたが、均等に糊をのばすのにはやはりサポートが必要でした。
作品を温風機で乾かして頂く間に再び展示施設棟に戻ってショッピングコーナーを見たりして過ごしました。
そして約30分後にいよいよオリジナルの「ランチョンマット」を受取りましたが、その出来栄えに皆さん大満足でした。
15時30分に染体験コースが終わり、一般見学コース同様、車組と徒歩組に分かれる為、工場にて解散しました。
「大松染工場」の皆様には、お忙しい中でご丁寧な研修及び個別指導をして頂き、心から感謝申し上げたいと思います。
小袖会としましては、第2回目の「きもの産地見学会」の開催に向けて、色々な観点から行き先・時期を検討して参りたいと思っております。企画決定次第、HP(ホームページ)や大江戸だよりを通じてご案内したいと存じますので楽しみにお待ち頂きますようお願い申し上げます。
【 小袖会代表 近藤君子 記 】
Views: 4
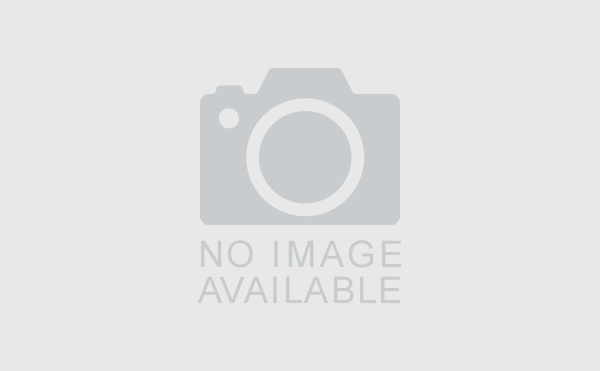
「江戸小紋」「江戸更紗」は現代風にもアレンジされ、粋な男性シャツや女性のお洒落なブラウスやストールにもなっていました。シワにもならず、通気性もよく時代を超えて現代に生きている感がしました。
とても貴重な見学、並びに体験でした。 小袖会の第一回目のイベントは大成功でしたね。
小袖会のみなさま
第1回「きもの産地見学会」に沢山の方が参加され、盛会でしたね
「大江戸だより第27号」の投稿で黒川さんが予告されておりましたが、伝統の匠の技を見学したり、染付の実体験をしたり‥と充実した時間を過ごされましたね。
第2回目の「きもの産地見学会」の開催と継続的な開催を祈念致しております。