マナビ塾:11月14日(金)修験道について学びました。
第6回のマナビ塾は、11月17日(金)に山伏の資格を持つ高橋利行氏による講義で、「修験道」をテーマに受講者23名が色々なことを学びました。
開始時間となり、「講師を紹介します」と言った司会者の後のバルコニーから突如、白装束姿で現れるオープニングの演出に皆さん度肝を抜かれました。

お話のイントロは、注目を浴びた山伏の装束の説明から始まりました。頭に付けているのが「頭襟(トキン)」で落石除けだったものが小さくなったもの、白い法衣は「鈴懸(スズカケ)」で修行で着用するもの、手に持つもので短くて金属の輪が付いたものが「錫杖(シャクジョウ)」で魔除け、長い四角の白木の棒が「金剛杖(コンゴウヅエ)」で登山具兼獣除け等の説明をして頂きました。
そしていよいよ本題が始まりました。ご用意したビデオプロジェクターの画像付きの解説でした。
[1]山伏とは何か
「山に伏す(寝泊まりする)」から「山伏」と言われるようになり、聖地とされる厳しい山で修行に励み、「験力(ゲンリキ)」と言う超能力を獲得することを目指すことから「修験者」とも呼ばれている。民俗学的には古くは「日知り(ヒジリ)」とも呼ばれ、「日=天体の動き」を「知るもの」即ち「暦」に詳しいもので、農耕に欠かせない存在でもあった。
⇒江戸時代は関所もフリーパス出来た生業で、明治初期には10万人以上いたとの話にビックリ!
[2]何故、山伏になったのか
40代の初めにNHK特番「出羽三山 秋の峰入り」を視聴し、山伏の修行に感動した記憶が残っていた中で、平成21年(2009年)に新田次郎著「剱岳<点の記(キ)>」が映画化されたので見に行った。あらすじは、明治時代、陸軍の測量隊が未踏とされて来た「剱岳」に苦労して登頂したところ、山頂で錫杖が見つかり、実は1400年前(奈良時代)に山伏が登頂していたことが判明したと言う物語であるが、改めて山伏に強く惹かれるキッカケになった。
⇒定年後に犯罪防止活動である「ガーディアン・エンジェルス」等のボランティア活動をやられていたとのことなので、元々身体を動かすのがお好きであったようです。

[3]どのように山伏になったか
羽黒派古修験道修行の「秋の峰入り」(出羽三山神社にて行われる6泊7日の修行)を手紙で申込んだが、神社や宿坊関係者が優先され、中々受付けてもらえなかった。ようやく平成28年(2016年)8月に参加出来た。
「擬死再生」(一度死んで地獄に落ち、穢れを消滅させて、生まれ変わる)を目的とした厳しい修行であったが、何とか終えることが出来、「補任(ブニン)状」を拝受し、山伏名「捷秀(ショウシュウ)」も与えられた。
⇒修行内容は、「聞くなかれ・語るなかれ」と厳命され、誓約書(血判指印)も提出されているとのことで概略のみお話し頂きましたが、修行終了時のお写真にその壮絶さを感じました。(68キロの体重が59キロになったとのこと)
[4]独自の霊山登拝修行の実践
「秋の峰入り」を20回行う満行参勤を目指す道もあったが、自分は全国にある他の修験道コースを体験する道を選んだ。(以下は例として掲載)

①平成29年(2017年)5月上旬(7日間)に「吉野(金峯山寺)~熊野本宮大社の奥駈け(逆峰コース:全長100km道中にある75カ所の靡(ナビキ)に立ち寄っての拝礼・唱和)」
②平成30年(2018年)8月下旬~9月上旬(7日間)に「比叡山千日回峰行(カイホウギョウ)の舞台となる無動寺回峰道(五里)と飯室回峰道(七里)の抖擻(トウソウ)を毎日実践」

③令和元年(2019年)9月中旬(4日間)に「立山三山・大日三山の縦走と剱岳登頂」
④令和5年(2023年)5月中旬(9日間)に「新宮大瀧(熊野那智大社)~吉野(金峯山寺)の奥駈け(順峰コース:全長130km)」
⇒剱岳に登頂した際には、山頂の祠の前で拝詞(神前で唱える祝詞)を行ったところ、いつのまにか自分の後ろに大勢の登山者が一緒に並んで拝んでいて、その中の一人からお布施までもらったとの面白いエピソードも聞かせて頂きました。
[5]今後の予定
今後も、独自霊山登拝修行として①日本三大霊山(立山・白山・富士山)、②剱岳(早月尾根ルートで再登頂)、③近畿・九州・東北の霊山巡り等を計画している。
⇒剱岳を「1400年前の山伏が登ったのではないかと言われる難関ルートで再登頂したい」とのお話をされた時の目の輝きに、講師の独自の修行に駆り立てるエネルギーの源をみた感じがしました。
[6]皆さんにお伝えしたいこと
国土の7割以上が山地である日本において、「山」は恵(水・木材・食物・動物)を与えてくれる半面で災い(火山噴火・土砂崩れ)ももたらすことから、「山」に畏敬の念を抱き、神聖視されるようになって「山岳信仰」が生まれている。自分は横浜市港南区に住んでいるが、毎日、富士山のある方向に拝んでいる。都会で暮らす人も山が見えた時に「自然に対する謙虚さ」を思い出して欲しい。
山伏の修行では、「奥駈け」のような修行ばかりでなく、歩きながら瞑想をする「歩行禅」と言うものもある。心のエクサザイズとも言われるものなので興味のある方にはお教えします。
⇒「歩行禅」には皆さん関心を持たれたご様子でした。
以上2時間の講義でしたが、修験道・山伏について豊富な資料とスライドを使って分かりやすくかつユーモアを交えてご説明頂き、かなり理解が進んだように思われます。更に70歳を過ぎられてからも次々と独自に修行を続けられている講師の前向きな生き方に感銘を受けられた方がかなりいらっしゃったように思われます。本当に有難うございました。
次回は、12月3日(日)下総中山駅改札口に10時30分に集合頂き、一緒に「中山競馬場」に行った上で、茂呂講師より「競馬概論と馬券の買い方の初級編」を講義頂きます。多くの方のご参加をお待ちしております。
【 マナビ塾世話役 栗原麗子 記 】
Views: 2
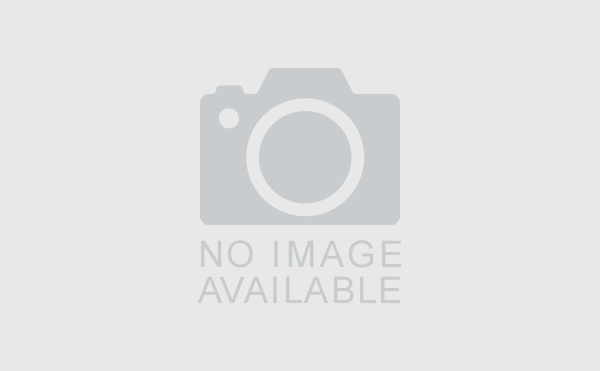
ニッセイOBの方が山伏になられたことにまず驚きました。私たちの知らない世界の沢山のお話をお聞きする中で、いつもと違う空気を吸って、気持ちが高揚する感じになった研修でした。
すごい方にお会いする機会を設けて頂いたマナビ塾スタッフの方々に感謝です。素晴らしいお時間でした。ありがとうございました。
お人柄の良さそうな山伏さんに感謝です。
成澤さま
本当にビックリでしたですね。講師の方の回りに清浄な空気が流れているように私も感じました。
栗原
拝読致しました~。 実際に受講した時のことを思い出すことが出来ました。
改めて、山伏と云う大変な修行を続けられている体力と精神力に尊敬致します!
高橋さま
お読みいただきありがとうございました。奥深い話でしたね。栗原
HPにて修験道を拝見しました。
髙橋利行さんの体力・気力と湧出するエネルギーに感服いたしております。
怠惰な私には到底まねのできないことですが、「自然に対する謙虚さ」は持ち続けて行きたいと思います。 ありがとうございました。
森岡さま
当日の雰囲気が伝わったみたいでよかったです。自然の中の私たち、まさに!
拝読しました。
当時「NHK特番」や映画「点の記」を私も見ていただけに、
修験道の道に進まれた高橋さんはよほどご縁があったのでしよう。
山を敬い大自然に畏敬の念を抱く山伏を筆頭とする多くの
日本人があったからこそ、今日全世界の観光客から日本は美しい国と絶賛されていると思いました。
マナビ塾「修験道」の記事を閲覧頂いた皆様へ
講師の高橋利行さんが、本部喜楽会HPの東京都支部紹介ページの「我が街のお気に入りの風景」に「元旦恒例の早朝トレイルラン」についての記事と写真を投稿されました。
ご自宅から3.5Kmにある横浜市最高峰の「大丸山(おおまるやま)」(標高156.8m)に毎年元旦に登っているそうです。(さすがに山伏の格好ではなくトレーニングウエアだそうです)
素晴しい朝日と霊峰富士の写真も掲載頂きました。是非、本部喜楽会HPに利用登録されている方はログインして閲覧願います。
事務局(HP担当)薮内