マナビ塾:3月8日(金)「ボクの細道」を通じて昭和の時代を一緒に振り返りました。
2024年3月8日 今年度最後のマナビ塾(第10回)は「戦後日本を生き抜いたサラーリーマン~ボクの細道」。講師と共に戦後復興・再生、そして今後の人生を見つめてみました!
弥生三月というのに前日は小雪が舞い雨模様の寒い日でしたが、今年度最後のマナビ塾が日生日比谷ビル喜楽会室で開催されました。

今年度のマナビ塾の棹尾を飾っていただいた講師は森瀬光毅様。喜寿を過ぎ傘寿に迫ろうとする今も企業の監査役、地域活動、宗教法人の役員等をお勤めになられていらっしゃいます。
同じ時代に共に働いた仲間たちと、その時代を振り返り、語り合い、学び合うことは貴重なこと。ご自身(ボク)の歩んできた決して平坦ではなかった人生旅路の細道の一端から、生後4か月で遭遇した太平洋戦争末期の東京大空襲での被災と東北地方への疎開、敗戦復興の中での同潤会上野下アパートでの生活、在学時に体験した東大安田講堂事件、目くるめく自由な、夢のような学寮生活、再生に関わられた同潤会アパートと母校小学校廃校イベント、日本生命入社時の大阪万国博覧会出展の思い出等々をサブ資料「昭和の時代を語ろう」や映像までご用意いただきお話いただきました。
昭和4年竣工の同潤会アパートも小学校校舎も関東大震災からの復興事業の産物・遺産。
森瀬講師のお話全体に流れる「私はなぜ生きるのか、生きているのか、人生は旅路、生まれた瞬間から「死に至る道」、何処まで続くやこの小道、マダマダ続くこの細道」、に感銘を受けました。
「今日は残りの人生の最初の日」「夢を忘れずに、年を重ねただけでは人は老いない。理想を失うときはじめて老いる」、「風にそよぐ葦の如く儚い存在だが、人間は考える葦である」、先人の言葉の引用もまたこれからの人生、天から与えられたこの命を大事に生きたいと思わせるものでした。ありがとうございました。
それでは森瀬講師のパワーポイントからの抜粋をご紹介させていただきます。
〇「ボクの細道: 死に至る道」
人は誰でも、この世に生まれてきた瞬間から「死に至る道」を歩み、そしていつか必ず死に至る。生まれてすぐに東京大空襲に見舞われ生家焼失、死に直面したが幸いにも死を免れ、そして「死に至る道」を歩み続けてすでに傘寿。ボクの細道「死に至る道」はマダマダ続く。

東大三四郎池付近、神護寺の写真に「どこまで続くやこの道」「この道や行く人なしに秋の暮れ(芭蕉)」のキャプションがついていました。松尾芭蕉と同様に本所深川、上野、千住に移り住み、今も「花の雲鐘は上野か浅草か」を感じる地に暮らし、「奥の細道」の影響を色濃く受けたものでしょう。
〇「細道が始まる時代環境」
昭和20年3月10日の東京大空襲はアメリカ側発表で334機のB29の大編隊による無差別爆撃が行われ、一夜にして10万人余もの一般市民の命が失われ、26万戸の家屋が焼失、100万人以上が罹災(重軽傷者、行方不明者)。昭和19年10月東京下町の本所区に生まれ、東京大空襲に遭遇し,生家を焼失、生後4ケ月の私は母親に背負われ、焼夷弾が降り注ぐ中、火で赤く染まった空を背に懸命に逃げのびた。
広島、長崎への原爆投下、ソ連の対日参戦、そんな時代です。
〇「敗戦からの復興と戦後」
秋田県に疎開した幼少期、厳冬の地の民家の軒先に立ち、そこから眺めた深い雪景色は今も脳裏に深く刻まれている。敗戦後の東京下町、上野恩賜公園内に溢れていた闇市と、戦争孤児の光景も目に焼き付いて離れない。登下校した中学も高校も上野公園の中にあった。
疎開先では東京っ子と言われ石を投げられた悲しい経験もおありだそうです。
〇「東京下町の戦争犠牲者たちの人生」
どんな人でも、ただ一度しか生きられない。人生のやり直しはできない。一度しかない人生だからこそ、有限だからこそ,愛おしさが増すのだろうか。人はある時代を意識して生まれるのではない。生れ落ちてみたらそれはある時代のある社会の中。その中で人は生きなければならない。それぞれの能力、意志によって生活を設計しなければならない。
誰しもが必死の時代、を彷彿とさせます。
〇「敗戦後の上野」
家から徒歩10分の下谷小学校は、狭い校庭には子どもたちで溢れかえっていた。貧しいながらも夢と明日への希望を抱いて、元気に遊び、学んだ。入学した年の4月にはマッカーサー元帥が帰国。終戦直後の上野公園、上野駅構内、地下道、アメ横、浅草公園周辺には戦争孤児や浮浪者があふれ、決してキレイとは言えない町だった。ユネスコ世界遺産に登録されている西洋美術館が建つ地には極貧の人々が肩を寄せ合い、西郷隆盛像が建つ地では、東京大空襲の後、多数の犠牲者の遺体が焼かれた。浅草の蟻の町。最盛期には1300名の児童が在学していた下谷小学校も人数減少からすでに廃校にと時の流れが滲みます。
〇「敗戦がもたらした同世代の中での溝」「神が人類に贈ってくれた宝物」
小中学校時代の仲間の中には、多くの戦争犠牲者が存在した。戦場に駆り出され死を余儀なくされた者が残した孤児や家族がおり、他方戦争指導層のこどもや孫たちも戦後を生きている。日本国憲法は素晴らしく「まるで神が人類に贈ってくれた宝物」という方もいる。日本国憲法の出来た過程の意味と昭和の時代の歴史を学び直すことが大切です。

〇「関東大震災と同潤会、そして上野下アパートが生きた時代」
上野駅から徒歩10分ほどの地下鉄稲荷町駅。日本初の地下鉄として昭和2年に開通した下町のシンボル。そこから徒歩1分の地に建てられた同潤会上野下アパート。関東大震災からの復興を担う財団法人同潤会が昭和4年に建て、84年の歳月を経て建て替えられた。戦後復興の過程で子どもたちの成長を見守り、建物の老朽化や居住者の高齢化の進行の中で様々なドラマが展開されたが、そこは小学校から大学を卒業して日本生命での転勤生活に入るまでの思い出深い住まいでもあった。忘れえぬ素晴らしい青春もそこに存在していた。
〇東大紛争とは何だったのだろうか」
造反有理・帝大解体・革命の夢破れ、多くの学友が逮捕され、その後の人生の歯車が狂った多くの学友たちがいた。現在の学園にはデモ隊も、立看も、ゲバ棒も、ヘルメット姿もない。「夏草や兵どもが夢のあと(芭蕉)」である。
〇「これからの人生行路(ボクの細道)」
迷い・悩みと大切な使命、心に太陽・くちびるに歌をみちづれに。
生きる力の源泉は「自分がこの世に生まれ、生きてきたことに思いをいたすこと」。
それは戦時下で救われた命、母からもらった命、母の面影に思いをいたすことでもある。両親に感謝の気持ちを持ち、両親はその両親に、累積する先人たちへの感謝の気持ちがある。
本所生まれの先人である芥川龍之介の自殺に興味を覚え、哲学者ニーチェのニヒリズムに共感を覚えた若者は、「人生とは?」「生きることの意味は?」という難題と取り組みながら、今や組織から自由で忖度も束縛もなく、徒然なるままに思いを致す。過去と未来に。現代の「方丈の庵」ともいえるマンションの片隅で、徒然草と方丈記を紐解きながら思索に耽る貴重で得難い日々を送っている。
「今日は残りの人生の最初の日」スタートは今、目標は社会貢献、生き甲斐と結んでくださった。
同潤会上野下アパートの取り壊しから14階建のマンション、ザ・パークハウス上野への再生実現に尽力された森瀬講師の生きてこられた道と重なり合う戦後、それはまた私たちの道でもあり感慨深いものを感じ味わった時間となりました。
悪夢の3月10日を目前にして、人生、生きること、戦争と平和、貴重な平和憲法への思いを改めて伝えてくれました。時間の関係から、平和憲法制定の歴史的過程への言及が出来ず名著「敗北を抱きしめて 第2次大戦後の日本人」:ジョンダワー著を紹介された。
最後に語られたのは、かけがえのない人生の応援歌、天からお迎えが来た時の断り文句。
「80才:傘寿:何の、まだまた役に立つ、困った人の傘になるのだ
88才:米寿:もう少し米を食べてからだ
90才;卒寿:卒業するにはまだ単位が足りない。未修科目が一杯だ」
パワーポイントの言葉、笑いながらの、それでいてこれからも続く私たちの人生を心強く後押しして下さり、勇気づけてもいただきました。感謝とともに御礼申し上げます。
今年度のマナビ塾は本講座をもって修了いたしました。ご登壇いただきました講師の方々、ご参加いただいた皆さまに感謝申し上げます。
なお2024年度の竿頭は6月27日(木)、森林インストラクターの西 隆昭氏をお迎えして開講いたします。奮ってご参加ください。
【 マナビ塾世話役 栗原麗子 記 】
Views: 5
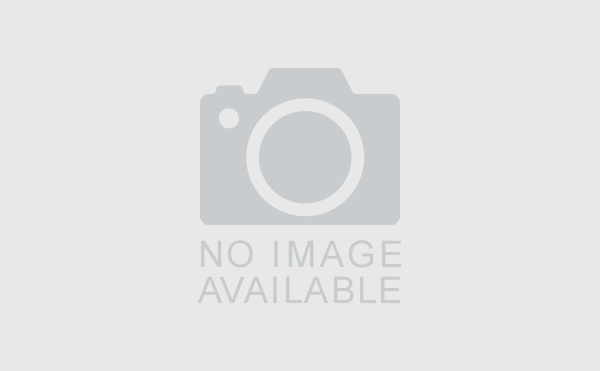
読ませて頂きました。特に森瀬様の幼少時の戦争体験は、横浜の焼けただれた街並みの中、祖母達を訪ね歩いたことや防空壕に入り赤い空を覗き見た我が身の思い出と重なり、懐かしき思いで一杯に成りました。
また、同潤会上野下アパートの住人として建て替えに腐心したお話や、地元の下谷小学校OBとして廃校イベントを開催されたお話をお聞きして「昭和の時代」を一緒に振り替えることが出来たように思います。
心より感謝です。スタッフの皆様ありがとうございました。
成沢さま
コメントありがとうございました。本当に光陰矢の如しですが、確実に私たちの経験してきた時代でしたよね。栗原
戦火の中、生を享けまさに命懸けで生き抜いてこられた森瀬講師のお話に、衝撃を受け、多くのことを教えて頂きました。
時にはユーモアを交えながら、死生観や生きることの意味等々、お話は多岐に渡り常に生きる指針を示して下さったように感じます。
ご用意くださった資料は大切な哲学書となりました。ありがとうございました。