マナビ塾:11月15日(金)「健康体操“自彊術”」を体験しました。
日比谷公園の銀杏も色づき始めた11月15日(金)、次々と日比谷ビル6階喜楽室に16名の方々がバスタオル持参でお集まりくださいました。
本日のマナビ塾は健康体操「自彊術(ジキョウジュツ)」の体験です。私たちの前に現れたのは、喜楽会室の床(カーペット)に素足で立たれた自彊術を17年続けていらっしゃる我が東京都支部(新宿G)の佐藤トメ子さんと佐藤さんが指導を受けている十文字自彊術健悠会の渡辺英子師範と丹生じゅん子先生のお三方でした。
受講する私たちも素足になって何が始まるのか興味深々、「膝や腰や肩が痛いけど付いていけるかなぁ」との参加者のつぶやきも聞こえる中で、始りました。
[1]私が自彊術を始めたキッカケとその効果~佐藤トメ子氏の体験談~

佐藤さんが自彊術を始められたのは、17年前にお客様のお宅でたまたま「自彊術」の教室から帰られたお嬢様が腰痛に悩む自分に勧められたことがキッカケだそうです。
以来、80才になられた今も続けており、持病の腰痛も治り健康でいられるとのこと。特にその効用を感じたのは、ある時、座ろうとした椅子が突然後ろに倒れ、お尻から落ちて「これは頭を打つ!マズイ!」と思ったとき、背中までは床に付いたものの首だけは瞬時に持ち上げられいて、頭を守れた時だそうです。
「自彊術」の良さは、無理をさせないことで、各人の身体に合わせて痛いところがあれば痛みが出ないように指導頂けるので、気持ちよく続けられるとのことです。
「今回は自分が通っている教室のお二人の指導者に事情をお話したところ、PRにもなるからと無料で実技指導を頂けることになりましたので、是非、その素晴らしさを体験して頂き、興味を持つキッカケになって頂ければ、幸いです。」とのお話を頂きました。
(注)佐藤トメ子さんの「自彊術」につきましては、本部喜楽会HP(東京都支部紹介ページ)の「私の稽古と学習(ケイコとマナブ)」の2022年12月8日付投稿記事にてもご紹介頂いていますので併せて閲覧願います。
[2]自彊術とは一体何か~渡辺英子師範の講義~

自彊術は大正5年の春、手技治療の天才といわれた中井房五郎氏が古代中国の手技療法(按摩・指圧・整体等)から考案された31の動作に凝縮された体操で、健康体操の先駆けでもあり、31の動作を順番に行うことで体に眠る「病気を治す力」を蘇らせるというものだそうです。
この「自彊術」の普及につとめられたのが中井氏の患者でもあった十文字大元氏で、大元氏の奥様が自彊術を正課とする「十文字学園」を創設し、そこで習得した生徒が起こした自彊術の本流が「十文字自彊術」で、その指導者たちが集まる会が「十文字自彊術健悠会」とのことでした。
「自彊術」を理解する上でのポイントとして以下のお話がありました。
①病気怪我を治す治療法から出来ている。
日本で生まれた自彊術は基本裸足、頭のてっぺんから足先、指先までを使い、関節は数千回動かすそうです。31の動作は約20~25分。短い時間ですばやく行い、関節の他に筋肉は十万超も刺激され、それは同時に整体、それも内臓の整体でもあり、内臓をあるべき位置に戻し病気怪我の予防や治療に繋げていくという考えが基本になっているそうです。
②胸式呼吸で行う。
呼吸法は、腹式と胸式とあるが、胸式で行うので、鼻から吸って口から吐く。風船をぱんぱんに膨らませて口を閉じパッと開くそのイメージで、鼻から吸ってハッと吐く。お腹を締めた状態で行うとのことです。⇒「いち」「にっ」と独特の号令を用いて行うので自然に身が引き締まるそうです。
③31の動作が一つの運動
31の動作は順番が決まっていて、一つの動作は次の動作への準備動作となっており、31の動作を全て順番通り行うことが重要とのことです。
④反動を利用する。
一つ一つの動作は弾みをつけてその反動を利用しているので、一見激しいようですが実はそれほどエネルギーを消費しないので弱いところを持つ方も安心して出来るそうです。⇒力まないことが大事ですよと仰っていました。
⑤左右同時の動作は、具合の悪い方に合わせる。
左右同時の動作は、具合の悪い方に合わせることです。膝がつけない方は椅子を使っても立っても、その時に自分ができる形で行うことが肝要ですとのこと。⇒これまたこころ穏やかに取り組めそうですね。
⑥他人と比較しない。
大事なことは人と比較せず自分の能力アップを心がけていただきたいとのこと。⇒隣の方が気になりますが自分は自分の気持ちで今回もやりましょう!
⑦どこでもいつでも行えるのでとにかく続ける。
そして自彊術の一番良いところは覚えるとどこにでも連れていける、道具も場所もいらず、畳一畳あれば出来るし、ご自分の具合の悪い箇所に効く動作を行うことも有効なので、とにかく毎日続けることが大事とのことです。⇒続けることで、身体貯金の筋肉が付き、寒さ暑さへの防衛、攻撃への防御にも繋がるとのご説明が印象的でした。
[3]31の動作の体験~渡辺師範・丹生先生による実技指導~

ここからは実際に自彊術の31の動作の体験で、渡辺先生の各動作のポイントの説明の後に、丹生先生が掛け声とともにお手本動作を見せてくれ、皆さんがそれに合わせて身体を動かして行きました。
まずは真っ直ぐ立ってみます。肩幅に開いた足、お腹と頭を上に伸ばし、かかとに体重、肘を伸ばして手を楽に。手を握って開いて、吸って吐いてを繰り返す。
次に吸って吐いて親指から小指まで一本ずつ順に開いてまた閉じていく。誰もが出来ている。誰もが一生懸命。更に応用で吸って吐いて左は親指から右は小指から一本ずつ順に開いて閉じていく。あれれもう混乱している人多数、笑い声が起きる。
渡辺先生から皆さん良い姿勢ですよと褒められて気をよくしつつ、以上の事前運動を行った後にいよいよ31の動作を第1動から体験して行きました。
第1動は呼吸運動。呼吸法の繰り返しで自律神経が整い、肩を上下させることで肩のマッサージ効果、高血圧の降下、腹部の引き締め効果。下腹周りを揉み解すことで胃腸下垂等々。“いっち、にっ” “いっち、にっ” お腹の底から出ているような力強い丹生先生の声に合わせ皆さん真剣。
第2動は肋骨を抱えて肩を上下する。手の平を胸部に当てながら肩を上下、胸部が広がり内臓のマッサージ効果、消化器内臓の伸縮、肝胆の血流増加等々。一段と力強い掛け声にみなさん真面目な取り組み。すでに身体が熱くなっている。
こうして第3動、第4動・・・と進み第31動までが終わります。

途中「無理は禁物、出来るところまでですよ。」と先生の声がかかりますが、どうしてでしょう。どなたも言われた動作をきちんとやろうとする意気込みがムンムン。
第30動はでんぐり返しでしたが、これは渡辺師範の実技のみでした。その柔軟な身体には皆さん感動しました。
以上、始める前よりも、血流が健やかに流れ、筋肉がほぐれ、関節が柔らかくなったことを皆さんが実感する二時間となりました。
佐藤トメ子さんには、渡辺師範、丹生先生の実技指導を通じて、身体に眠る「病気を治す力」を蘇させる「自彊術」を体験する機会を設けて頂いたことに心から感謝申し上げます。
次回は 12月24日(火) 13:30~ 「タンパク質の王者~卵の驚異の秘密に迫る」です。鳥インフルルエンザ等々から値上がりしている卵、その効用に改めて考える講座になっております。お楽しみに。
大勢の皆様のご参加をお待ちしています。
【 マナビ塾世話役 栗原麗子 記 】
Views: 5
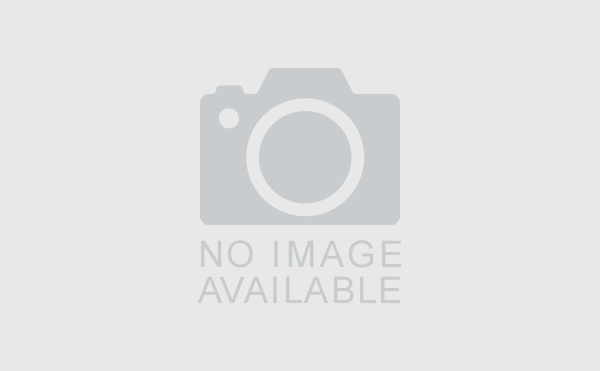
佐藤トメ子さん
自彊術(じきょうじゅつ)の講話、ありがとうございました。
「大江戸だより第26号」の会員だより欄で、佐藤さんから「自彊術との出会い」と題して投稿頂き、自彊術の素晴らしさを教えて頂きました。
加えて、当記事にて講話の様子を拝見し、能楽堂の楽屋のお仕事もされながら、いろんな同好会
に参加されている‥佐藤さんの「元気と幸せの源」を知ることが出来ました。
じきょうじゅつ
マナビ塾に参加し 身体に眠る病気を治す力 への体験 今まで知りえなかった 事に出会うことが出来 この先元気一杯に 過ごせる思いに成りました 素晴らしい体験 ありがとうございました 佐藤先生にお会いできたことに 幸せを感じます スタッフの皆様に感謝です