マナビ塾:12月24日(火)「タンパク質とビタミンの重要性」について学びました。
12月24日(火)のマナビ塾は、奈良からお見えくださった大江康男講師をお迎えして開催しました。クリスマスイブにもかかわらず20名の方々が集われ、「タンパク質の王者~卵の脅威の秘密に迫る」の題でタンパク質とビタミンの重要性について学びました。

[1]なぜタンパク質に興味を持つようになったのか
最初に大江氏がなぜタンパク質に興味を持つことになったかのお話から入りました。
大江講師のお孫さん(当時、小学6年生)が多動性障害(ADHD)の傾向が見られ、落着きがなく、その上にアトピーと喘息を持っていたそうです。
何とかならないものかと調べていたところ精神科医である藤川徳美先生のご本「うつ消しごはん」に出会い、うつ病等の治療に「鉄フェリチン」を重視している考え方に着目されたそうです。
更に藤川先生のお考えの元になったのが物理学者の三石巌先生が提唱されていた「分子栄養学」(後述)であることを知り、三石先生のご本もたくさん読まれたとのこと。
“鉄”は血液の赤血球の中のヘモグロビンとなって全身に酸素を運ぶ役割を担っている為、不足すると貧血になることは有名ですが、実は心の安定ややる気に関係する「セレトニン」や「ドーパミン」という神経伝達物質を作る過程で補因子としても重要な役割を担っています。(他にも「活性酸素の除去」や「細胞のエネルギー代謝」にも関わっています)
つまり鉄不足は貧血だけでなくうつ病や統合失調症等の精神病の発症要因にもなると言うことです。
この鉄はヘモグロビンとして血液で利用されるもの以外はタンパク質のひとつである「フェリチン」と結合して「鉄フェリチン」として肝臓に貯蔵されることから「貯蔵鉄」とも呼ばれているそうです。
よって鉄不足か否かを判定するには、「ヘモグロビン値」だけでなく「フェリチン値」も調べる必要があります。
ところがお孫さんの「フェリチン値」の血液検査をしようとしてもなかなか検査のできるところが見つからず腐心されたとのこと。
やっと調べたら33と基準値100を大きく下回っていることが判明し、直ちに三石式「健康自主管理」すなわち「高タンパク質+メガビタミン(大量のビタミン)+スカベンジャー(活性酸素退治:カロチノイド・ポリフェノール等)」に基づき、ホエイプロテイン(牛乳由来のタンパク質で消化吸収が早いプロテイン)とキレート鉄(吸収しやすい鉄)とビタミンC等を飲んだところ、僅か2カ月で症状が治まったとのことです。その後、運動能力・学力とも急上昇し、高校3年生の時に100m走で11秒フラットを記録、須磨学園から東大理2に現役合格したそうです。
この体験が、その後、大江氏が三石先生及び藤川先生やその他の先生方の書籍で勉強されるキッカケになったとのことです。

[2]分子栄養学について
次に、三石先生の「分子栄養学」について概略を説明頂きました。
従来の栄養学は、タンパク質を体重の1/1000摂取するという量的な基準しか示さないのに対して、「分子栄養学」では、良質なタンパク質を体重の1/1000摂取するように示しているとのこと。
良質とはタンパク質の元になっている20種のアミノ酸、しかもその内、人間が自前で作れな9種の不可欠(必須)アミノ酸を含んでいるとのこと。
実は、人の体の細胞は次々と作り替えられていて、その際、DNAの指令でアミノ酸が様々な順序で並べられて10万種類のタンパク質を作っているそうです。
なお、新しいアミノ酸がないと古いアミノ酸を使用してしまい、それが色々な病気の原因になっているそうです。だからこそ「良質なタンパク質=高タンパク質を毎日とりなさい」と言うことになる訳です。
良質なタンパク質を何から摂取するかと言うことですが、不可欠(必須)アミノ酸を100%含んでいる食物を「プロテインスコア100」と表して、様々な食品の「プロテインスコア」を表にされています。
その中で“卵”が「プロテインスコア100」だそうです。ちなみに肉魚90~80、米65、大豆56、食パン44だそうです。
しかし、体重の1/1000摂取は、中々大変です。“卵”1個は平均7gしかないので、体重70Kgの人は70gとるために卵を10個食べなくてはいけないことになります。牛肉200gでも30gなので卵をあと6個食べなくてはいけません。よって不足分はプロテインで補うように指導されています。このプロテインは英語のproteinであり意味はタンパク質。語源はギリシャ語で「一番大切なもの」を意味するproteiosに由来しているそうです
次に「分子栄養学」のもう一つの柱であるでは、「メガビタミン」の必要性を説明させて頂きます。
体内で作られる10万種のタンパク質は、人間個々に作る能力に個体差があるので、例えば免疫力に関わるタンパク質を作る能力が低い人はそれだけ病気に罹りやすくなるそうです。
では、どうするかですが、タンパク質を作る能力は、酵素タンパクと協同因子(言わば“サポーター”)として働くビタミン・ミネラルの量と相関しているので、特にサポーターとして大きなウエイトを占めるビタミンを摂取すれば良いとのこと。
但し、たくさんあるビタミンの内、どのビタミンが必要かを判断することが出来ないので、ならば「大量のビタミン=メガビタミンを摂取しなさい」と言うことになる訳です。
なお、藤川先生は食べ物でビタミンを摂取するのは難しいので適宜色々なビタミンのサプリメントを利用することを勧められています。
<参考図書>①「分子栄養学のすすめ:健康自主管理の基礎知識」三石巌著、②「医学常識はウソだらけ」三石巌著、③「すべての不調は自分で治せる」藤川徳美著
[3]タンパク質の王者“卵”のお話
次に本題のタンパク質の王者“卵”のお話に移りました。
前述の通り“卵”は全ての不可欠アミノ酸を持つ「プロテインスコア100」の完全栄養食です。
但し、生卵は、生の卵白に含まれるアビジンがビタミンH(後述)の吸収を阻害するのでゆで卵がお薦めとのことです。
ゆで卵一個分Sサイズ位(50g)での栄養価は、タンパク質が6.3g、脂質が5.2gとなるとのこと。
卵黄にはレシチンとよばれるリン脂質の一種が含まれ、リン脂質は細胞の膜を作る主要成分で、レシチン・リゾレシチンセファリン等々からなっており、レシチンは脳の発育に必要な栄養素だそうです。
更に凄いのは、ビタミンは13種類中Cを除きすべて含まれていることです。
代表的なものは、①ビタミンAは目や皮膚の健康保持、②ビタミンDはカルシウムの吸収の促進、③ビタミンB2はエネルギー産生に関与、④ビタミンB12は赤血球の合成に必要、⑤ビタミンEは血管の若返り、⑥ビタミンHは体内の糖やアミノ酸・脂質の代謝に働く
また、ゆで卵は栄養価が高いのに比べ脂質が少なく低糖質なので、ダイエット中にオススメの食品でもあります。
ごはんとの比較では、ごはん150gが234Kcal・糖質53g・タンパク質2.5gに対して、卵3個は 200 Kcal・糖質0.6g・タンパク質19gとなります。
ところで、「卵の摂りすぎはコレステロールを上げる」と言われていますが、三石先生によれば、国立栄養研究所の研究員が1日10個の卵を2カ月食べてもコレステロールは上がらなかったとのことです。
そして、あのドジャースの大谷翔平選手は多い時には1日14個のゆで卵を食べていたそうですが、今でも朝昼晩3個ずつ食べているそうです。
[4]その他の関連情報
以上のお話を踏まえて、高齢者の多い受講者向けに関連情報のご説明がありました。
(1)タンパク質に関わる血液検査について
以上のように重要なタンパク質については、血液検査の次の2つの項目で状況が分かるそうです。
ひとつは、「アルブミン」です。アルブミンは主に肝臓で合成される血漿タンパク質ですが、細胞への酸素や栄養素の運搬や血管内外の液体バランスを保っており、血漿中のタンパク質の60%を占める重要な役割を担っています。
語源はラテン語の「白」で“卵”の白身からきています。そうなんです。卵白部分には特に多くのアルブミンが含まれているのです。
アルブミンの値は3.9以上欲しいとのこと。低いのは問題あり、特に2.5にまで下がると回復への道のりは低いと言わざるを得ないとのこと。
もうひとつは、「BUN(尿素窒素)」です。BUNはタンパク質が体内で代謝されたのちにできる老廃物のことで、腎機能を見る場合の測定値ですが、タンパク質の過不足をみるものでもあります。BUNは20以上欲しいとのこと。
アルブミンとBUNを見て、タンパク質の不足が判明すれば、プロテインを摂取して欲しいとのことです。
(2)ビタミンEの重要性
ビタミンEは強い抗酸化作用を持つ脂溶性のビタミンで、体内の脂質の酸化を防ぎ、動脈硬化や血栓の予防、血圧の低下、細胞膜の健全化等加齢によって発症しやすい疾患の予防になるので、「若返りのビタミン」とも言われているので喜楽会員の方には特にお薦めとのことです。
(3)マグネシウムについて
マグネシウムは、筋肉の収縮、神経の伝達、エネルギーの生成等に関わる重要なミネラルで不足すると不整脈や虚血性心疾患や高血圧等になりやすいので摂取して欲しいとのこと。
海藻類と塩に含まれるが、塩については一般の精製塩はマグネシウムが除去されており、「毒塩」になってしまうから、マグネシウムの入った「天然塩」を使うようにとのことでした。

[5]最後に受講者間の意見交換
以上のお話をお聞きした後に、四人一組になってのグループ・ミーティングで「日ごろ健康に留意していること」をテーマに意見交換の場を設けて頂きました。その中で趣味・運動・睡眠の他に食事のメニューも付け加わったのは本日の講義の効果のように思われました。
各グループの結果発表者には講師からご用意いただいたプレゼントが渡され、和やかな雰囲気の中で終了しました。
大江講師には遠く奈良からお出まし頂き、豊富な資料をもとに有意義なお話を通じて「自分の健康は自分で!」と改めて思い定めることが出来るご講演を有難うございました。
そしてプレゼントのご用意までして頂き感謝の言葉もございません。
次回は、1月29日(水)13:30~15:30勝田和行講師(写真同好会代表)をお迎えして「スマホで撮れる”映える写真”」を喜楽会室で開催いたします。
大勢の皆様のご参加をお待ちしています。事前にご連絡をいただけますと幸いです。
【 マナビ塾世話役 栗原麗子 記 】
Views: 9
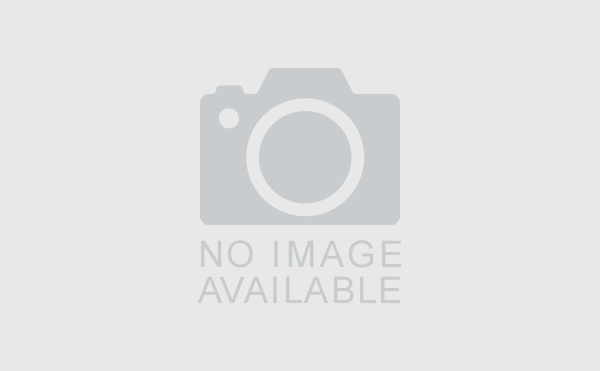
大江先生のお話をお聞きして、改めて日々の食生活から身体は作られるのだと認識いたしました。特に良質なプロテインである卵を積極的に献立に取り入れていきたいと思います。また、鉄分、ビタミン、ナトリウム等の栄養素の大切さや血液検査の見方等大変勉強になりました。
奈良からお越しくださった大江先生、栗原様をはじめ幹事の皆様、素晴らしい勉強会を有難うございました。
私は学び塾に参加できませんでしたが、この文を読み大変感銘を受けました。お孫さんの体験もこの上なく素晴らしく、卵の栄養素に改めて目から鱗の感でした。
シニアながら日々筋トレをし、プロテインを飲んでいますが、やはり食事から栄養素を摂ることが基本ですね。卵を毎日2-3個は食べる様にしています。本当に為になる講演 誠にありがとうございました。
気になっていた講演でしたが,記事を読ませていただき,思っていたよりも,有意義な素晴らしい内容に感動致しました!
遠方の奈良からお越しいただき,それも感謝ですね 卵も常に冷蔵庫には切らさない様に入ってますが,何と今、切れてました!早速買いに行きます,まずいつもの倍は食べる様にしたいです