マナビ塾:2月28日(金)セカンドライフを楽しむ法の一つとして「有料老人ホーム」を学びました。
2月28日(金)、早春の一日、「セカンドライフをいかに楽しむか、そのひとつの選択肢として、有料老人ホームとはどのようなものなのか」について、小野信夫講師より学びました。
日本生命のOBでもある小野講師は、ALPS開発部の商品開発グループに所属時に私たちには懐かしい「三大疾病保険”あすりーと”」の名称発案者でもあるのですよと明かしてくださいました。
そして生命保険文化センター・ニッセイ基礎研・ニッセイ聖隷健康福祉財団を経て、2008年に学校法人和洋学園に転職され、研究支援課長や国際交流センター事務室長を担当されたそうです。
その後、2010年4月からは「日本老人福祉財団」に再転職され、京都ゆうゆうの里施設長やサービス支援部長・企画室室長を担当されて現在は理事として財団の経営に携わっていらっしゃいます。
冒頭、「本日は営業に重点をおいていませんのでご安心下さい。」と私たちをと笑わせながら、以下の講義が始まりました。(注:花粉症がひどいとのことでマスクを付けながらお話し頂きました。)

[1]セカンドライフ・サードライフの暮らしをイメージする
まず、セカンドライフとはいったいどのように位置づけられるのかの説明から入りました。
一つのイメージとしては、以下の通りとのこと。
①ファーストステージ ・・・現役世代(65歳位までをイメージ)
②セカンドライフ ・・・アクティブシニア(65歳~70歳位 :元気いきいき)⇒自立高齢期(70歳~80歳位:まだまだ元気) ⇒フレイル(80歳~90歳位 :健康な状態と要介護状態の中間で筋力低下、倦怠感、骨粗鬆等が生じてくる)
③サードライフ ・・・要介護 (90歳位~)
もちろん個人差はあり、生涯現役とばかりにファーストステージを継続中でフレイルの心配がない方もいらっしゃるが、そのような方でも要介護になり得るのは事実、その時期をサードライフと位置づけしたとのこと。
その上で、受講者の私たちに「将来の暮らしへのイメージ」を考えて欲しいとのことで、次のステップで配布資料の記入欄に書くようにご指示頂きました。
(1)セカンドライフとサードライフにどんな暮らしをしていたいか
(2)その暮らしを実現するためにどのような「自然環境・生活環境・社会資源(医療機関等)」及び「人的資源(家族・友人等)」が必要か
(3)その「自然環境・生活環境・社会資源(医療機関等)」及び「人的資源(家族・友人等)」は、現在充足されているか、また将来(例えば10年後)も充足されているか
(4)将来も含めて充足しているのであれば、自宅で暮らし続けることも良いが、もし、希望する暮らしを実現するための環境や資源が不足しているのであれば、高齢期の住替えの要否を検討
受講者には考える時間(約20分程)を与えられましたが、将来の自身及び家族・友人の健康の変化や経済的な変化等を考えると希望する暮らしの実現に向けて環境や資源が充分整っているとは言えないことに皆さん気付かされたのではないでしょうか。
このことが、次の「高齢者むけ住まい」への関心を高めさせることになりました。実に上手な講義の展開です。
[2]高齢者向けの住まいについて
高齢者向け住まい・施設の種類として、以下の6つがあり、各々の根拠法、基本的性格、施設の定義、利用できる介護保険の有無、施設の設置主体、入居対象者の条件等を説明頂きました。
①特別養護老人ホーム(いわゆる“特養”)[根拠法:老人福祉法20条-5]
②養護老人ホーム[老人福祉法20条-4]
③軽費老人ホーム(いわゆる“ケアハウス”)[老人福祉法20条-6 社会福祉法65条]
④有料老人ホーム[老人福祉法29条]
⑤サービス付き高齢者向け住宅(いわゆる“サ高住”)[高齢者住まい法5条]
⑥認知症高齢者グループホーム(いわゆる“グループホーム”)[老人福祉法5条-2]
要は、入居者の所得(低い~高い)と自立度(自立~要介護)に合わせて色々な種類の施設があるということが理解できました。
[3]有料老人ホームについて
ここからは高齢者向け住まいの一つである有料老人ホームについて詳しいお話がありました。
実は有料老人ホームは「高齢者向けの住まい」+「高齢者むけのサービス」と定義されているそうです。
「高齢者むけのサービス」には 1)食事の提供 2) 介護の提供 3)洗濯、掃除等の家事 4)健康管理があり、法律上はどれか一つが行われてれば良いとのこと。
「高齢者向けの住まい」の法律上の定義としては、老人福祉施設(特養)や認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホーム)を行う住居そのほか厚労省令で定める施設(老健)でないものと明記されているそうです。
また有料老人ホームの種類には「健康型」「住宅型」「介護付き」と三種類あるとのこと。
「健康型」は食事等のサービスがついた高齢者向け居住施設ですが、介護が必要になった場合は契約解除し退去しなければならないタイプ。⇒実際の施設としてはほとんどない。
「住宅型」は生活支援等のサービスがついており、介護が必要になった場合は入居者自身の選択により地域の訪問介護等の介護サービスを利用していくタイプ。
「介護付き」は介護等のサービスが付き、介護が必要となった場合は当該有料老人ホームが提供する介護サービスを利用するタイプ。
なお、入居する際の要件も、元気な自立されている方のみ、自立・要支援のみ、要支援・要介護のみ、要介護のみ、要件なしと様々あるとのことでした。
ちなみに「ゆうゆうの里」は介護付き有料老人ホームの分類に入り、入居時自立されている方が要件となっており、元気なうちに入居のプライムタイムを楽しむことを目的とする施設だそうです。
[4]有料老人ホームの歴史
有料老人ホームの成り立ちは1960年代の老人福祉法制定から始まりますが、近代的な有料老人ホームとしては、1973年の聖隷福祉事業団の「浜名湖エデンの園」、1976年の日本老人福祉財団の「浜松ゆうゆうの里」が先駆けとのこと。
2000年に介護保険制度がスタートすると、介護事業は、超高齢化社会の中での有力な成長産業として有料老人ホーム及びサービス付き高齢者住宅の施設数が急増したとのこと。(参考:有料老人ホームの施設利用者数:2000年36,855人→2021年590,323人)


[5]日本老人福祉財団「ゆうゆうの里」について
「日本老人福祉財団」は1973年に設立され、入居時自立型の介護付き有料老人ホーム「ゆうゆうの里」を運営し、1976年の浜松を第一号として1979年伊豆高原、1983年神戸・湯河原、1985年大阪、1988年佐倉、1997年京都と全国に7ケ所に展開しているとのこと。
7ケ所計では入居者総数2,552名、職員数1,175名、管理栄養士、栄養士、調理師による完全直営の食堂、診療所を併設しているとのこと。
また、創立50周年記念で製作された各施設の動画を見させて頂きましたが、綺麗で大きな施設内で入居者の皆さんが趣味(絵画・ギター・フラダンス・園芸等)やスポーツ(水泳・卓球・ジム)のサークルで楽しむ様子を見させて頂きました。入居率が95%と人気が高いのも納得しました。
さて、気になる入居費用ですが、千葉県の「佐倉ゆうゆうの里」の直近の価格表によりますと、1人用の1Kの部屋(31.8㎡)の場合は入居金3219万円、2人用の1LDKの部屋(52.2㎡)の場合は入居金5272万円、2人用の2LDKの部屋(60.9㎡)の場合は入居金5661万円とのことでした。(施設によって価格は変わるとのことです。)
他に月々の生活費(管理費・食費・水道料・給湯料・電話代)として1人入居の場合は約14万円で2人入居の場合は約25万円がかるとのことです。
なお、入居金はア)入居一時金(施設を終身利用するための家賃に相当する)とイ)介護等一時金とウ)健康管理一時金から構成されているとのことでした。
[6]入居時自立型「介護付き有料老人ホーム」の選び方
入居時自立型の介護付有料老人ホーム選びのポイントは、次の2点とのこと。
(1)自分が求めるものは何か整理すること(立地・建物の共有部分・医療/介護の充実度・食事/行事の充実度等)
(2)自分なりの優先度を決めておくこと(介護の不安解消・仲間作り・自分の時間の確保等)
更に見学時のポイントは、①入居者を観る、②職員を見る、③時間帯や季節を変えたりして何度も施設を訪問する。(出来れば宿泊する)

[7]入居時自立型「介護付き有料老人ホーム」での暮らしのポイント
最後にAI(ChatGPT)が出してきたという、入居時自立型の介護付有料老人ホームの生活を楽しむコツ(10のポイント)の説明がありました。要するに「積極的に楽しもうとする力」と「手伝って、助けてと職員に声をかける受援力」が重要とのことでした。
以上の講義を通じて、受講者の皆さん方は将来の暮らしを考える良い機会となった上に、高齢者むけ住宅及び有料老人ホームに関する知識を深めることが出来たように思います。
カラー刷りの素晴らしい資料をご準備頂き、分かりやすくお話し頂いた小野講師には心より感謝申し上げます。
次回は 3月28日(金) 13:30~「街道ひとり歩きを楽しむ」のテーマで中村昭氏を講師に迎えて開催いたします。どうぞ皆さま楽しみに、お申込みをお待ちしております。
【 マナビ塾世話役 栗原麗子 記 】
Views: 7
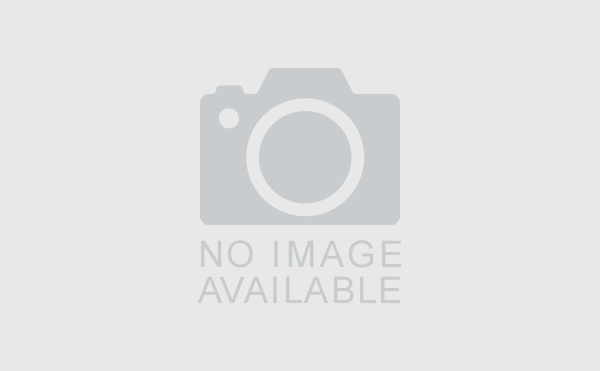
有料老人ホームの新聞折込広告が毎日のように入ります。その内容はどれもホテルのような豪華さで、入居費用の高さに驚かされ、自分とは縁のないものだと思っていました。今回のマナビ塾で、講師の小野様より様々な介護施設の特徴や違いを詳しく教えていただきました。今は元気に過ごせているお陰で介護施設について考えることはありませんでしたが、これを機に、自身が要介護となった場合どのように余生を過ごしたいのかを、今のうちから家族と話し合っておく必要があると思いました。講師の小野様、幹事の栗原様、沢山の資料とお話をありがとうございました。
昔若かりし頃、「二十歳の設計」と言う源氏鶏太さんの小説の影響で「B・G(ビジネスガールのこと、今のOL)」の生き方に憧れましたが、その計画は、実家のある八戸を襲った二度の災害のお陰でみごとに実現出来なくなりました。1度目はチリ地震南米の津浪の影響で家が流され、2度目は放火による大火でした。やはり住まいは人生を考える上で重要な土台であると思います。
現在は、歳老いてしまいましたが、セカンドライフからサードライフを計画しなくてはいけなくなりました。今回の講義では、老いてもなお明るく充実した日々を送るための方法を高齢者むけの住まいから考える良い機会になりました。小野先生どうも有難うございました。
上野G 成澤節子
成澤さま
実感のこもった感想をいただきありがとうございます。サードライフはすぐそこですが、ちょっとだけ先送りにしたいものです。あきらめずに前を見ようでまいりましょうか。栗原