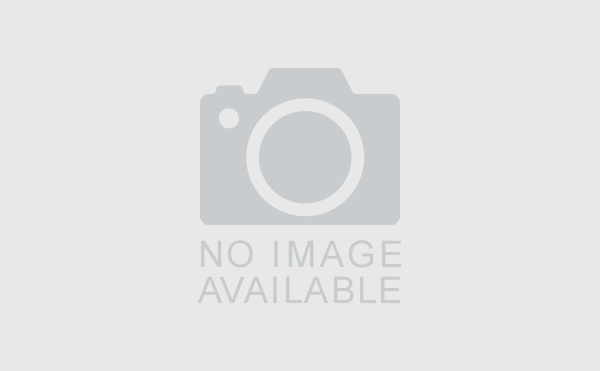マナビ塾:7月25日(金)「読み手と聞き手の心が繋がる朗読」を体験しました。
今年度第2回のマナビ塾は、7月25日(金)に「読み手と聞き手の心が繋がる朗読」をテーマに渋谷Gの長谷川知子さんを講師としてお迎えし、受講者22名がお集まり頂きました。
講師のご指示で座席は5~6名の4グループになるように配置して、講義が予定の13時30分から始まりました。

[1]講師の自己紹介
まず初めに長谷川講師よりご自己紹介として、朗読との出会いと現在朗読にどのように関わっているのかについてお話がありました。
・トレーナーやFPを生かした営業の一線から65歳の定年を機に退職し、新たに打ち込める趣味を探していたところ、ニッセイ時代のお客様に誘われて一緒にNHK放送研修センターの朗読研修会を2016年に受講したことをキッカケに、現在も元NHKエグゼクティブ・アナウンサーを講師としてグループレッスンを受けている。
・一方で、朗読を学んだ仲間同士の研鑽の場であると同時に公演活動も行っている朗読のサークルにも興味を持ち、現在は、①目黒区の教職員方が立ち上げられた歴史のある「朗読サロンひととき」(練習は月1回)や②朗読のためのヴォイストレーニングを柱にした「おなかのへるヴォイストレーニングの会」(練習は月2回)、そして③”朗読サロンひととき”の仲間三人で立ち上げた「朗読会ICHIE(イチエ)」(練習は月2回)の3サークルに加入している。
・更に、ボランティア活動として、下目黒小学校や同図書館等での子どもたちへの絵本等の読み聞かせを継続して行っている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで世話役の私(栗原)より朗読サークルの公演がどのようなものか、マナビ塾の直前の7月5日(土)に長谷川講師が出演された「おなかのへるヴォイストレーニングの会」主催の朗読会「ぎくしゃくとかくしゃく」を鑑賞した時の写真と感想の形で以下補足説明をさせて頂きます。

公演では、詩や本の一節の朗読を舞台の前に数名ずつ出て朗読されていました。当然、声の高さや声の質や大きさ等が異なるのですが、それが個性となって楽しめることに驚きました。そして何よりも驚くのは、出演者20数名の中に90才代の方もいらっしゃるのに、実に声が通るのです。また、全メンバーによる合唱もあったのですが、これがまた合唱団顔負け位にお上手なのです。
2時間程の公演でしたが、(1)自分を見つめれば年老いて若い時のようにうまく動かない頭と身体の状態に、(2)世界を見つめれば軍事強国が隣国に攻め込む状況に、「ぎくしゃく」さを感じることの重要性と、それに対して自分はどうしたら「かくしゃく」として生きて行けるのかを考えることの重要性を気付かせてもらえたような気がしました。朗読の訴える力は素晴らしいものがあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[2]グループ内での「朗読の3ステップ」の体験
次に講師よりA4一枚に印刷された漱石「坊ちゃん」の一節が資料として全員に配布され、各グループ毎に①黙読・ ②音読 ・ ③朗読の3ステップで読むように指示がありました。

・文字を言葉にする上で、①黙読 →②音読→③朗読の3ステップを踏むことは極めて重要である。
・まず初めに「黙読」することが基本となる。声を出す前に、作者の意図をつかみ、文章の朗読を通して聞き手に何を伝えたいかを明確にするスッテップである。
・次に音読をする。抑揚をつけずに声をだして読む。読めない字、初めての言葉、読みづらいところ、噛みやすいところ、文章の意味と切れ目、強調するところ等をマークしたり、その作品らしい雰囲気を捉え、どんな感じて読むかを決める。(ただし、今日は、人数が多いので各自控え目に音読して欲しい。)
・最後がグループ内での朗読となる。①②で考えたことを元に読んでいき、互いにどこが良かったかをコメントし合って欲しい。朗読は相手があって初めて成立するものなので、聞き手にいろいろ意見を言ってもらうのが一番上達に役立つ。
⇒皆さん数分で黙読を済ますと、なんだか気恥ずかしいような音読があちこちから聞こえて来ました。独り言のように声を出す人、早口な人がほとんどでしたが、資料にメモや線を書き込んでいる方もいます。やがてグループ毎に一人ひとりの朗読する声とそれに対するメンバーの評価が聞こえてきました。
⇒「意識的に間を取っていたのが分かる」、「声が聞き取りやすい」、「セリフに感情がこもっていた」等誉め言葉がほとんどの中で、「時間を気にされたせいかもしれないが少し速かった」との指摘も聞こえました。中には「今の父親だったら二階から飛び降りる行為をまず叱る。腰を抜かしたことを叱る昔の父親は威厳があった。」等と時代背景について感想を述べる方もいらっしゃいました。
しばらくすると講師より、「坊ちゃん」の資料に①強調したい箇所(高く、強く、ゆっくり等)、②間をとりたい箇所、③感情を込めたい箇所、④鼻濁音「が」の箇所の表示と欄外に⑤セリフの部分は他の部分と読み分けるとの注意点が朱記されたもう一枚の資料が配布され、朱記部分を注意して読むように指示がありました。
⇒するとあら不思議!その後のメンバーの朗読が一本調子的だったのが、明らかにメリハリがついてきたのです。まさに指導効果を実感出来ました。
[3]聞き取りやすい「美しい声」を出すための発声練習
次に、講師が作成されたテキストをもとに声を滑らかにする発声練習方法を解説頂きました。
・「美しい声」は大きく口を開けて一語一語はっきり発すれば出ると思うのは間違いで、実は朗読では大きく口を開けて声は出さない。口は開けるのはだいだい口幅どまりでお腹から「アッ アッ アッ」と声をだす要領つまり腹式呼吸法(腹筋・背筋を使って息を吐き切り、体全体を使って息を吸い込む)を使っている。
・「美しい声」を出す姿勢としては、喉・鼻腔・口腔・腹腔をフル活用し、それでいて口にも唇にも顔にも余分な力を入れず、肩の力を抜き体の重心を下のほうにしてリラックスすることが重要。
⇒講師の促しに、講師の口元を見ながら必要最小限に口を開けて「アッ アッ アッ」・「イッ イッ イッ」・「ウッ ウッ ウッ」と皆な一斉に声を合わせてみる。確かにはっきりした声が伝わってきます。声の出し方として大きく口を開ければよいということではないということに目から鱗の方も多かったのではないでしょうか。
・発声練習としては、母音練習として「あいうえおあお、おあおえういえあ」を、滑舌練習として「あいうえお いうえおあ うえおあい えおあいう おあいうえ」・「かきくけこ きくけこか くけこかき・・・・」を50音全て繰り返す方法がある。
・滑舌練習としては、他に「だ・ざ・ぱ・ら行」の練習も有効で「だぞ ざど どざ ぞだ 」・「らだ らだ りだ りだ」等から更に早口練習として「だぞざど どざだが」・「ぼぱるば ばるぱぼ」等を繰り返す方法もある。
・滑舌をよくする方法としては、「舌回し運動」~舌で歯を一本ずつ触っていく、上の歯から下の歯へ、下の歯から上の歯へ、8回ほど回していく~で舌の筋肉を鍛えるのも有効である。
⇒講師が皆さんにトライさせましたが、母音練習すら全くそろわず、残念ながら発声練習は短時間で終了しました。
[4]朗読の効用
次に講師が9年間朗読を続けて来て感じた効用について以下のお話がありました。
・腹筋を使って発声することで、口・喉(ノド)・声帯・気管周辺の筋肉が鍛えられている。そのことを通じて、高齢者の多い朗読サークルの仲間たちからは、次の4つの効用があるとの声を聞くことが多い。
①ほうれい線はくっきり、口角が上がり、小顔になる。
②肺活量が増え、誤嚥性肺炎の予防につながる。
③無理のない、自然な発声をすることで声が美しく変化する。
④滑舌がよくなり聞き取りやすい声がでる。
⇒「特に④は話相手に自らの言葉を伝えることにもなり、日常生活の中でも大いに役立つので、発声練習は朗読のためばかりではありませんよね。」との講師コメントには、皆さん大いにうなづいていました。
[5]発声前の準備運動
講義が1時間経過したところで休憩を取り、その休憩明けの冒頭に朗読サークルで行っている発声前の準備運動をご指導頂きました。

・スポーツと同じで、良い声はリラックスした体から生まれるので、発声前には軽く体を動かして欲しい。体が温まりほぐれてくると声が出やすくなる。
⇒講師の指導の下に3つの体操をすることになり、①首を前後左右に曲げゆっくり回す、②両手を上げ下げ→両手を肩にあてて回し→肩甲骨を動かす、③前屈し両手を前にだらりとおろし上半身をぶらぶらゆする→ゆっくり背骨の骨を一本ずつ意識して丁寧に上半身を起こす、の3つの体操を実践しました。なお、コーラス同好会の会員でもある受講者の方からコーラスも似たような体操を発声前に行っているとのことでした。やはり発声と言う点では共通するものなのですね。
[6]皆さんの前での朗読体験
最後に受講者22名全員が皆さんの前で「ぼっちゃん」の一節を読むことになりました。

5~6名の前で読むよりも緊張する環境になったにも関わらず、講師から頂いた注意点が意識され、準備体操で血流が良くなったことで、テンポ・メリハリ・声の出し方等がグループ内での朗読とは明らかに良くなったことを受講者全員が感じられたのではないでしょうか。
講師からも「真剣に朗読に取り組んで頂いたことの成果が大いに現れ、大変嬉しく思います。」とのコメントを頂きました。
なお、皆さんから講師の朗読をお聞きしたいとの要望にお応え頂き、朗読の締めとして黒柳徹子の書いた「少女たちの戦争」という本の中の一遍「スルメ」を読んでくださいました。
出征する兵隊さんを町内で小旗を振って見送ると「スルメ」がもらえたので、喜んで見送りに参加していた幼少期の自分(黒柳徹子)も戦争に加担していたのではないかと言う筋のエッセイですが、終戦から80年を迎えた我々に色々と考えさせる内容でした。朗読のお上手さはもちろんのことこの一遍を選んだ講師に皆さん大拍手でした。
手作りのパワーポイントのテキストをご用意頂いた上に、一方的なお話しだけでなく朗読の魅力を体験する講義を企画頂いた長谷川講師には、改めまして感謝申し上げます。間違いなく朗読に興味を持たれた方が複数人はいらっしゃると思います。有難うございました。
次回は 8月26日(火) 13:30~「日本百低山 踏破の旅」を加藤浩二氏を講師に迎えて開催いたします。どうぞ皆さま楽しみにお申込みをお待ちしております。
【 マナビ塾世話役 栗原麗子 記 】
Views: 58