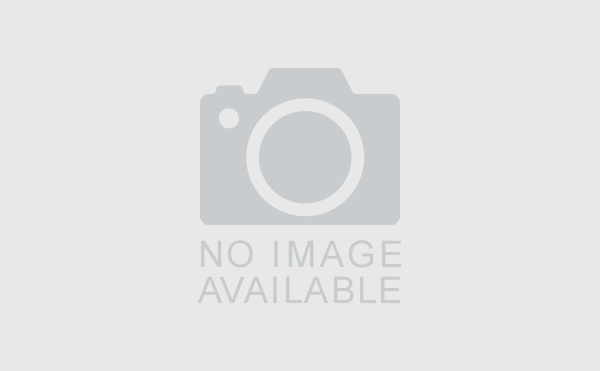マナビ塾:8月26日(火)「低山の楽しみ方」について学びました。
8月のマナビ塾は、標高50㍍以下の「超低山」に登り続けていらっしゃる加藤浩二氏を講師にお迎えして、何故に超低山を目指されたのか、その魅力、そして低いから簡単と侮れない危険な山もあることなど豊富な体験をもとに二時間、尽きせぬお話に引き込まれたのでした。
加藤講師は実は日本百名山や300名山といった名だたる山々を完登、制覇されてもいらっしゃるのですが、「低山倶楽部」というホームページを開設する低山ブームの草分け的存在でもあります。

「低山俱楽部」を覗いてみるとNHKを初めとしてテレビ朝日・日本テレビ、NHK第Ⅰ・文化放送・ラジオ日本・FMヨコハマといったTVラジオに何回もご出演。「おはよう日本」や「マツコ&有吉の怒り新党」など良く知る番組名もありました。
そして日経・朝日・毎日・読売といった新聞各社でも「想定外が楽しめる低山徘徊のススメ」や「そこに低い山があるから」等々低山の魅力を語る加藤講師が掲載されておりますし、登山誌「岳人」でも日本中に散らばる超低山へ登り続ける加藤講師の活躍が取り上げられていました。
そう加藤講師は知る人ぞ知る有名人だったのです。

〇現在登頂391座
講師の定義する低山は
1)国土地理院の25000分の1地形図にしょう肩体として名前が載っていて
2)標高50m以下もしくは都道府県の最低峰(13県) の二点です。
国土地理院の関氏が全国の地形図すべてを調べた低山リストでは全国に155座。その低山すべてを登りつくした後は、地形図に名前は載っていないものの地元では愛着をもって名前が付けられている山を含めて現在の登頂数は391座を数えるそうです。
数の多さに驚かされるとともに、この国土地理院の関氏とは地図標記について意見交換をされているよし、年期の入り方が違うとさらに驚かせられました。
それにしても意外だったのは、地形図を作る担当者やそのときの時流によって「この山はもう乗せなくていいかな」というケースがあるということです。低山数には出入りがあるということなのですね。2005年当時は149座だったそうです。

〇低山に目覚めたきっかけは
在職中の2000年6月大阪出張の際、天保山(大阪市港区)を訪れたのがきっかけ。江戸末期に土砂を積み上げた築山で、地盤沈下により93年に国土地理院の地形図から抹消され、地元の要望で96年に再掲された曰くつきの「日本一低い山」。標高4.53m。安治川下流の公園に三角点とともにひっそりとたたずんでいますが、そこからの雄大な眺めと秘められた歴史を思い出して感慨にふけられたとのこと。たった数歩で登ってしまったのですがこの天保山が低山遍歴の始まり。当時発行されていた「日本一低い山登山認定証」はなんともユーモアあふれるものだったと懐古されておられました。
ここでちょっと寄り道、三角点について。
三角点とは、日本の正確な位置を示す国家基準で、三角測量に用いられる基準点のこと。明治時代に全国の地図を作成するために陸軍測量部が測量、国土地理院に受け継がれ現在に至っていますが、なんと横浜市長津田が起点であり、一等三角点は973ケ所、二等三角点は5000ケ所、三等三角点は32000ケ所設置されているそうです。日本一高い山富士山にある三角点は二等三角点だと聞いて皆さん「へー」
〇低山の楽しみのひとつは情報量の少なさにあり
百名山などとは違って、低山は基本的に情報量が少ないのだそうです。現在はインターネットで多少のことは分かるようになりましたが、登り初めた当時はほとんど情報がなく、紙の地形図で山の形を確認して、どうやって登ろうかと登り方を考えながら現地に入ったり、近隣に住む方々にお話を伺ったり、また藪に覆われて道のない山もあり山の周囲をぐるっと歩き、どこからが比較的登りやすいかを考えて「藪漕ぎ(藪をかき分けて進むこと)」をしながら登ったお話もしてくださいました。苦労はありましたものの、楽しみでもありましたとのこと。
なんともパイオニアとしての開拓精神全開!です。
現在は加藤講師ご自身がインターネットに情報を載せたり、また低山俱楽部に情報を寄せてくださる方もいらっしゃるとのこと。昨今の低山ブームを引っ張る存在であることもうなづけた次第です。
〇低山155座制覇からみた低山といえども侮れない山々
2000年6月の天保山を皮切りに2005年1月までの5年間、北は北海道のサロベツ原野の「丸山」13.4mから南は沖縄県那覇市の「城岳」33.8mまで149座(当時の低山リスト掲載全座数)をクリアしたといいますからその行動力たるや驚異のレベルです。次いで少し間が開いていますが2019年4月にリストに追加された小笠原父島の飯盛山、新潟県の稲荷山等々残り低山も完登、全155座をクリア。
思い返せば一日に数座まとめて登ることもあったし、米軍基地内とか古墳内とか登れない山や沖縄ではハブの心配までしたりと、苦労部分も聞かせていただきました。
なかでも低山だからと侮れない山のお話は印象深く、


- 静岡県の安倍川の中州ににある「舟山」7mは、流れが深く、鮎釣り用の靴を履いての再挑戦でのやっとの踏破
- 愛媛県の海岸沿いにある「忽那(クツナ)山」49mは、茨に囲まれた藪山。「藪漕ぎ」で傷だらけとなり、服に穴をあけながらの30分、やっとの思いでの踏破
- 広島県の西能美島にある「茶臼山」11mは、地形図では砂浜にあるのに実際は50m位先の海の中。二時間干潮を待ってようやく踏破。テレ朝の番組で登り難い山と紹介しました
- 新潟県村上市の笹川流れ海岸の「鳥越山」50mは、断崖絶壁。オーバーハングになっているところもあり登頂断念。テレ朝ではクライミングの達人に登ってもらいました
- 長崎県対馬市浅芽湾にある「通山」38mは、リアス式海岸で島から伸びた細長い半島の道路から1km先端にあり、獣道を辿り踏破
等々、ご紹介いただいた山々だけではない想像するよりも過酷な環境の中での登山体験に難しさと加藤講師の挑戦へのあくなき探求心を感じました。
現在は地形図に山名表示はないものの地元では昔から山と呼ばれている里山や富士塚など、標高50m以上の低山を含めて新たな挑戦をされている加藤講師は、踏破数391座。まだまだ山々の背景にある物語とともに日本中の低山を遍歴して楽しんでいかれるとのこと。どこまで完登数を伸ばされるのか楽しみですし、加藤流“日本再発見の旅”を応援したい思いで一杯になりました。
〇最後に「日本一クイズ」とお薦め「花のお江戸低山散歩」
クイズ 日本一と名のつく低山にどんなものがあるの?

| 山名 | 選定根拠 | 高さ(m) | 山名 | 選定根拠 | 高さ(m) |
| 日和山(仙台市) | 半人工の山(東日本大震災後に復活) | 3m | 筑紫岳(秋田県) | 幻の日本一(今は地形図から削除) | ▲5m |
| 天保山(大阪市) | 三角点のある山 | 4.5m | 笠山(山口県萩市) | 火山 | 112m |
| 蘇鉄山(堺市) | 一等三角点のある山 | 6.9m | 大潟富士(秋田県) | 人工の山 | 0m |
お薦めのお江戸低山散歩

講師ご推薦、地下鉄銀座線沿線の江戸情緒あふれる低山です。
| 山名(場所) | 高さ(m) | 見どころ |
| 待乳山(浅草) | 9.7m | 東京都で一番低い山、三角点あり、大根のお供えが有名 |
| 擂鉢山(上野) | 23.3m | 上野の御山の一角にある、実は古墳 |
| 愛宕山(虎ノ門) | 25.7m | 男坂・女坂がある、馬で急坂を駆け上がった曲垣平九郎の逸話で有名 |
日本には富士山から始まる名だたる名峰山々が連なっていますが、地形図に記載のない名もなき山もまた多く存在しています。山が荒れると川が荒れ、海もまた痛む。加藤講師は地元の里山を保全するボランティア活動にも参加されていらっしゃるとのこと。無意識に通り過ぎてしまいがちな身近な山、森。改めて本日の「低山遍歴」のお話を聞かせていただいて、自らの着眼点を見直してみたいと思いました。
講義の中で活発に質問や意見の交換を受け入れてくださり、塾生のみなさんと一体になったご講演を休憩もなさらず完遂いただけてありがたく御礼申し上げる次第です。
次回は 9月30日(火) 13:30~「民生委員のお仕事!」を後藤彰氏を講師に迎えて開講いたします。また違った角度からのご登壇、どうぞ皆さま楽しみにお申込みをお待ちしております。
【 マナビ塾世話役 栗原麗子記 】
Views: 122