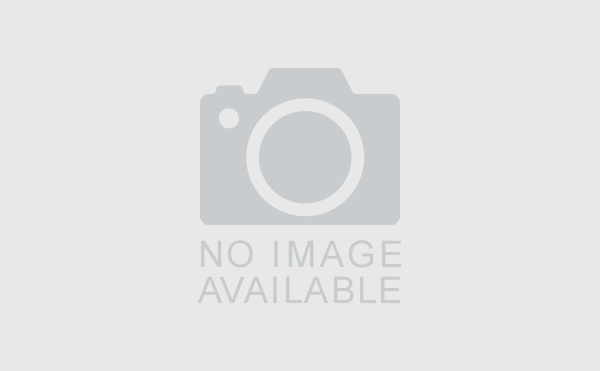マナビ塾:9月30日(火)「民生委員のお仕事」について学びました。
9月のマナビ塾は東京都北区で民生委員としてご活躍の後藤彰氏を講師にお迎えして、知っているようで意外と知らない”民生委員”の役割やその活動についての実際をお話いただきました。

後藤氏はまだ一期三年しかやっていないので経験が少ないと謙遜されつつ、所属する北区民生委員児童委員協議会高齢福祉部会での経験から学んだことやN社時代の同期103名の現在模様から感じるフレイル予防(後述)・介護予防の大切さを含め、改めて私たちにコミュニティ、社会参加というものについて考えさせる機会をいただきました。
それにしてもテーマの生真面目さとは別に、笑いで始まり絶えず笑いの起こる愉快な進め方、思わずお話に引き込まれたのでした。

〇民生委員になった経緯とは
何故民生委員になったのでしょうか。その問いに、「民生委員とは、厚生労働大臣の委嘱を受けて地域で活動する、相談・支援のボランティア。それぞれ担当の地域 (講師は北区) をもって必要に応じた福祉サービスを受けられるよう関係機関や団体等と連携する“区民と行政を結ぶパイプ役”なのですが、定年後暫く経ってからでしょうか。町内会の副会長をしていた私の父の関係からお祭りの手伝いを頼まれて、その縁で民生委員の引退時期にあたっていた前任者からお話をいただき、引き継ぐことになったわけです」とのこと。
実は民生委員には年齢要件があり、新任は67才未満でなければならず、すでに68才になっていた後藤講師は対象外だからと高を括って依頼を聞き流していたそうです。ところがどっこいそこには補足事項”地域実情により70才未満”も可能との例外規定があって、抜き差しならなくなったのですよ、と苦笑い。
白羽の矢が立てられ、外堀を埋められていったその時の様子を語られる後藤講師の姿に可笑しみとともに面倒見の良さの側面が窺えた瞬間でした。

〇北区民生委員・児童委員について
1)民生委員は児童委員を兼ねている
民生委員は民生委員法によって定められ、その第1条では「社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、および必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努める」ことを任務とすると記されています。そして児童福祉法により、民生委員は児童委員を兼ねるとされており、児童や乳幼児、妊産婦等の福祉や保護等のための相談や援助も行うことになっているとのことです。
講師の所属する北区民生委員児童委員協議会は定数323名、10の地区で構成されていて、地区協議会毎に子育て支援・児童福祉・障がい福祉・生活福祉・高齢福祉の5部会に分かれ、いずれかに所属活動することになっている由。講師は高齢福祉部会に所属されているとのことでした。加えて二期目に入った今年は高齢福祉部会の会長に就任された由。人口比の高齢者占率が高まる中責任が一層重くなっていっているようでした。
※北区のデータ (令和7年9月1日現在 ):総人口 366,965人(内65歳以上83,693人 22.81%) 世帯数 215,783世帯
2)民生委員は非給与・報酬なし
民生委員法第10条には給与を支給しないものとし、その任期は3年と記されています。給与のない、非常勤の特別職の地方公務員(都道府県)の身分なんですね。
その選任基準には、先に述べました年齢要件、そして北区議会議員の選挙権を有し、人格識見高く、広く社会の実情に適し、かつ、社会福祉の増進に熱意があり、児童福祉法の児童委員としても適格である方と続いていきます。
ご本人は人格識見はあまり高くないと謙遜されていて皆大笑い。
では活動に必要な経費はどうなんでしょう? の疑問が浮かびましたが、日々の活動に必要な実費相当分を「活動費」として月額11,300円(但し互助共励会会費等一部控除あり)が支給されると説明いただきました。隣人愛の精神なくしてはできないことではないかと感じ、考えさせられも致します。
3)民生委員の担っている職務内容は
民生委員法第14条で職務内容が5項目にまとめられています。1条の任務を具体化したものですが
・住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくことから始まり、
・援助を必要とする者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言、援助を行う
・援助必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供・援助を行う
・社会福祉を目的とする事業を経営する者、活動を行う者への支援、社会福祉法に定める福祉に関する事務所他関係行政機関の業務に協力すること等 まで。
そこには、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分または門地によって、差別的又は優先的な取り扱いをすることなく、実情に即して合理的に行わなければならないとの厳然とした基準が存在しています。との説明。
常にクォリティの高さを求められることへのリスペクトの念とともに、必要以上に踏み出さないようにしつつ、求められるときを逃さず適切な支援につなげていく、出過ぎず出なさすぎずの微妙な匙加減とでもいうのでしょうか、注意深く見守る存在であることを教えていただきました。

4)北区民生委員の主な活動は
講師が担当するエリアは北区西ヶ原の中の400世帯。二人の民生委員で担当されているとのことでしたが、子どもの姿は少なく、高齢者が目立つといった地域特性にあるようです。
そのような中での日々の活動には、「地区協議会への出席」・「総会への出席」・「社会福祉協議会への協力」・「各種研修等への参加」・「部会活動」に「活動記録集計報告書の提出」・「区民からの依頼による意見書・調査書の作成」等、多岐にわたるもので、これをもう少し詳しく見てみますと
・避難行動要支援者の把握と名簿の管理・・・現在20名をフォローしています。昨今の気候変動からの水害水没・地震等の際のサポートがあげられますが、担当地域は高低差の少ない高台なので水害水没の危険がないことは幸いだと思っていますとのこと
・生活保護を受けている方からの相談等をケースワーカーに取り次ぐ・・・見守り中の受給世帯が数世帯いらっしゃるのですが、3年間で相談はなかったとのこと。相談はケースワーカーとなさっているのでしょうと。
・一人暮らし高齢者定期訪問相談・・・これは65歳以上の方々で見守り依頼のある方を安心センターと連携しながら定期的に訪問していく制度ですが現在定期訪問はゼロだそうです。とはいえ担当地区の高齢者は161名と決して占率的に低いとは言えず注意が肝要と感じているとのこと。高齢者地域自立支援ネットワーク専門協力員としての活動に通じるものとのことでした。
このほか敬老祝い品贈呈事業への協力(北区は米寿と100歳の方に祝い金・祝い品贈呈)や高齢者ふれあい食事会事業へのお手伝い、社会福祉協議会の会費(寄付金)の集金等々、中でも夏場の会費集金は大変だったなぁと一言。そうそう町内会と連携しての夜回りへの協力!なんていうものもと。
また哀しい体験として「高齢者とはいえないものの60歳、アルコール依存で無職、食事をとれないほどの状態なのに配食サービスを受けるのを拒否され、看護師さんと月一回の訪問で伺ったところ、空いたドアの向こうに亡くなられている姿を発見してしまった」ことを語ってくださいました。個人情報を気遣いながらの最小限のお話でしたが、65歳以下の人たち(高齢者の括り外)はどこがフォロー対応するのかなぁとぽつんと一言。
こうした様々な相談支援に向けた活動を積み重ねてみますと、どんなに控え目にみても忙しいしフットワークが求められる活動。頭が下がります。
面白いことに敬老祝い金のお話のとき、受講者の方々から「自分たちの地区では〇〇円だった」とか、「喜寿でもいただいた!」とかの声が上がり、行政地域によっての違いが期せずして見えたのでした。
「でもね、できる範囲でやってください。決して一人で頑張らないでくださいと言われているのですよ」と講師。
民生委員の仕事の性質上、個人の力だけではなく地域や行政さまざまな支援を活用していくことこそが大切であり、個人に負荷をかけ過ぎないようにと配慮する言葉なのだろうなと拝察しました。
また参考までにと北区の民生委員・児童委員の活動広報ビラを見ながら解説いただきましたが、そこには「地域の皆さんの相談相手です」・「区民と行政を結ぶパイプ役です」・「地域で安心して暮らせるよう見守ります」・「地域のアンテナ役も務めています」・「福祉情報をお知らせします」の文字が踊っていましたし、「子どもや家庭の悩みごと~育児・DV・いじめ・引きこもり等々~への相談支援を行っています」も目を引きました。
課題の多い社会の中で民生委員を活用してもらいたい、知っておいてほしいとの意図、活用せずとも済む社会であれば良いなと思ったりもいたしますが、やはり制度を知っておくことは大事なのですね。
もちろん民生委員のなり手を掘り起こす意図もあるようです。東京都の民生委員と児童委員の平均年齢は65.2歳。退職後に委員になられる方も多い一方で40代の方もいるとのこと。半数以上が仕事をもちながら活動しているということには目から鱗でした。

〇高齢者福祉部会から学んだこと
ここからは角度を変えて所属されている北区民生委員児童委員協議会高齢福祉部会での経験やN社時代の同期103名の現在模様から感じるフレイル予防(後述)・介護予防について講師とともに一緒に考えてみよう!との時間。参加型で進められていきました。
1)フレイル予防~健康寿命を伸ばそう~
講師曰く、フレイルとは、年齢とともに筋力や認知機能など心身の活力が低下して、要介護状態となるリスクが高い状態をいいます。「虚弱」とも評されますが”健康”と”要介護”の中間ですね。
先日N社の同期会があり103名中39名の出席があったのですが、欠席連絡の近況覧をみるとどう見ても27名はフレイルではないかと推察できるのです。日本の男性の健康寿命は72.57才といいますから、まさにドンピシャその年齢に当たっているわけです。ちなみに女性の健康寿命は75.45才だそうですよ。
そこでやってみよう! というわけで全員で”フレイルリスク度セルフチェック”に取り組みました。
“体力” ”栄養 ” ”社会”に分け計15問。チェック結果点数を出しながら、ワイワイガヤガヤ。
あら~どうしましょう! 講師の狙い通り自分自身を見つめ気づく時間でした。
ではフレイルを予防するにはどうするか、フレイルには体重が減る、疲れやすい、握力が弱くなる、歩くのが遅くなるなどの兆候が出てきます。予防に遅いことはないので フレイルの予防習慣「3プラス1」を実践してみましょう。
3の1 “体力;歩く力筋力をつけるために動く” ・・・ 毎日10回スクワット
3の2 ”栄養 ;たんぱく質をしっかり食べる” ・・・ 合言葉は「さあにぎやかにいただく」で、①さかな、②あぶら、③にく、④ぎゅうにゅう、⑤やさい、⑥かいそう、⑦いも、⑧たまご、⑨だいず、⑩くだもの
3の3 ”社会参加;外出し人や社会とつながる”・・・ マナビ塾参加の皆さんは社会参加はパーフェクト。まったく心配はありませんが、絵・写真・読書・麻雀、なんでも頭を使うことを推奨します
プラス1”口腔;噛む飲み込む力お口の健康”・・・ あ~とん~を3回繰り返し噛む筋肉をつける
またもや合言葉当てにワイワイガヤガヤ
2)認知症について知ろう
誰しもかかる可能性のある認知症は身近な病気でもあるわけです。認知症は早く気づくことが大事であり、その上で介護保険サービスを利用するなど生活環境を整えいけば、生活上の支障を減らしていけると高齢者福祉部会にかかわって一層思うことでもあります。
そこでやってみよう! というわけで全員で今度は”自分でてきる認知症セルフチェック” に取り組みました。
またもやワイワイガヤガヤ。皆さんちょっとの不安を抱きながら、そしてホッとしながら点数交換いている人もいらっしゃいました。
以上、民生委員のお仕事を伺いながら、フレイルや認知症、介護保険やその申請の流れといったことまで幅広くお話いただき、その関係を良く理解することができた時間でした。
民生委員とは私たちの身近な問題と直結していることを、そして社会参加、人や社会とのつながりの大切さを改めて気づけた時間でもありました。
後藤講師にはご講義の中で活発に質問や意見の交換を受け入れてくださり、塾生のみなさんと一体になった時間をありがたく御礼申し上げる次第です。
また民生委員任命後交付される「民生委員・児童委員手帳」を見せていただきありがとうございました。
次回は 10月28日(火) 13:30~「太極拳と私」を小林真砂子氏を講師に迎えて開講いたします。また違った角度からのご登壇になると思いますので、どうぞ皆さま楽しみにお申込みをお待ちしております。
【 マナビ塾世話役 栗原麗子 記 】
Views: 117