ハイキング同好会:6月5日(木)北鎌倉~鎌倉散策に行って来ました。
6月5日(木)、さわやかな風の吹く絶好のハイキング日和に北鎌倉駅の東口に参加者24名全員が定刻のAM9時20分前にお集まり頂きました。

最初に千代田Gの中村G会長より本日のコース概略説明とガイドさん2名(鎌倉ガイド協会所属)の紹介を頂いてから、直ぐにA班11名、B班13名の2班に分かれて出発となりました。今回もガイド協会が我々の為に資料「鎌倉の歴史の一端をのぞいてみよう!」を用意して頂き全員に配布しました。

まず最初に向かったのは、「浄智寺」で鎌倉五山第4位のお寺です。(ちなみにR4年からの全ての鎌倉散策に参加された方はこれで全ての鎌倉五山を拝観して頂いたことになります。)8代執権の北条時宗の弟の宗政の菩提を弔うため、夫人と子供の師時が創建されたとのことでした。
山門の前にアジサイが咲いていたので写真を撮ったのですが、暗くて写らず、更に山門の有名な扁額「寳所在近(ホウショザイコン)」も写らず申し訳ありません。「寳所在近」とは、「宝(悟り)は、遠くにあるのではなく、あなたのすぐ近くにある。」と言う禅宗の教えとのことです。

山門を抜けると二階が鐘楼と言う珍しい鐘楼門が見えました。中国(宋)からの渡来僧が多く、宋風の様式だそうです。B班はしっかり鐘楼門をバックに写真を撮りましたが、A班は手前にあるツバキとアジサイを優先した写真を撮りました。

本堂は、「曇華殿(ドンゲデン)と言う三千年に一度だけ咲く伝説の花の名前が付いていました。中にあるご本尊は「三世仏(サンゼブツ)」と呼ばれるそうで、「阿弥陀如来・釈迦如来・弥勒如来」の三体の仏像が並んでいました。それぞれ過去・現世・未来の仏様だそうで、三世に渡り人々の願いを聞き入れてくださるそうです。
書院の裏庭を過ぎたところには竹林がありましたが、幹が四角張っている「四方竹」だそうです。

竹林とやぐら(石の山を掘った横穴で僧侶の修行場所や高貴な人のお墓に利用)を見ながら境内をほぼ一回りしたところにトンネルがあり、その先に大きなやぐらの中にある布袋尊がありました。鎌倉七福神の一人だそうです。お腹をさすると元気がもらえるとの説明にタッチする方が多かったようです。
境内からの出口は山門横にありました。

浄智寺を出て鎌倉街道沿いに鎌倉駅方面に歩くと「長寿寺」があり、その横が「亀ヶ谷(カメガヤツ)坂」と言う切通の上り口になってました。建長寺の池の亀がこの坂を上って行ったが急坂で引き返したことから「亀返坂」と言われ、それがいつの頃か「亀ヶ谷坂」になったとの伝聞があるとの説明がありましたが、皆さん亀のように引き返すことなく全員通り抜けられました。
なお、上り口のすぐ横にアジサイがキレイに咲いてました。また、坂の頂上を過ぎた下りの途中には切通が如何に大変な土木作業だったかを物語る高い壁面もありました。

「亀ヶ谷坂」を下ったところに小さな六角形の「岩船地蔵堂」がありました。源頼朝の長女の大姫の守り本尊と言われる地蔵尊が祀られていると言われていたが、最近の研究では次女の乙姫の守り本尊との説が強くなったとのことでした。
大姫は12歳で木曽義仲の息子の義高と婚約しましたが、義仲が頼朝と敵対して討たれた後に義高も逃亡途中で殺害されたことで心に傷を負い、その後、後白河法皇の皇子との縁談も断り、未婚のまま20歳で亡くなったことから「悲劇の姫君」として能や文学に登場しているそうです。そのため大姫のご本尊になってしまったのではないかとのことでした。

「岩船地蔵堂」を拝観した後、直ぐ近くのやぐらにある「相馬師常(モロツネ)墓」に寄りました。有力御家人の千葉常胤(ツネタネ)の次男で、磐城の相馬家の養子となり、奥州征伐で多くの戦功をあげた人物とのことでした。
その後、最後に向かったのが「浄光明寺」でした。5代執権北条時頼と6代執権北条長時が創建したとされますが、この寺を歴史的に有名にしたのは、鎌倉幕府滅亡後、足利尊氏が謹慎していた寺であるとともに後醍醐天皇への挙兵を決断した寺でもあるからだそうです。
謹慎したのは、「建武の新政」が始まった後、北条氏残党が一時的に鎌倉を奪還した時に、尊氏が後醍醐天皇の許可を得ずに独断で鎌倉に出陣して残党を討伐したことで、後醍醐天皇から謀反の疑いをかけられることを避けるためだったとのことでした。
但し、後醍醐天皇が新田義貞を大将とする官軍を差し向けたことで、やむなく挙兵を決断し、結果的に後醍醐天皇側の軍を打ち破り、室町幕府誕生に繋がって行ったわけです。
以上の説明の後に山門を抜けて境内に入ると正面に細長い階段があり、その上に仏殿がありました。
仏殿には、浄智寺と同じく「三世仏」が祀られていましたが、本尊は「阿弥陀三尊」とのことで仏殿の横にある「収蔵庫」に安置されていました。この「阿弥陀三尊」は、阿弥陀如来を中央に右に観世音菩薩、左に勢至菩薩が並んでいました。なお、「阿弥陀三尊」は、「土紋装飾」と言う鎌倉特有の技法が使われているとのことでした。
「仏殿」の裏手に更に急な階段があり、大きなやぐらの中に「網引(アミヒキ)地蔵」が安置されていました。由比ガ浜の漁師の網にかかったものとの伝説があるとのことでした。
そして更に階段を上がると裏山の山頂に「冷泉為相(レイゼイタメスケ)の墓」がありました。歌人藤原定家の孫で、歌道の名門冷泉家の始祖と言われている方とのことでした。
但し、我々が感動したのは山頂からの眺望でした。鎌倉の街並みとその先に由比ガ浜の海が見えたのです。皆さんご自分のスマホで写真を撮られていました。
「浄光明寺」を後にして解散場所の鎌倉駅西口に向かって歩いていましたが、参加者24名の内22名が懇親会に参加されることから、会場の「二楽荘」に近い鎌倉駅の手前にあるJR横須賀線の踏切の手前の空き地で急きょ解散することになりました。
解散に当たり、世話役の私(薮内)から歩く速度の遅いメンバーがいることを踏まえたコース設定と分かりやすい配布資料をご準備頂いた鎌倉ガイド協会のお二人に謝意をお伝えさせて頂きました。


なお、「二楽荘」では、「これで3000円の会費では申し訳ない」との声が聞こえるほどの美味しい中華のコース料理が出されましたので、皆さんの満足度は相当高かったように思えました。
今回もガイド協会との事前打ち合わせ及び懇親会場の手配を頂いた中村さんには、改めまして心より感謝申し上げます。とともに、11月13日(木)の鎌倉散策につきましてもよろしくお願い申し上げます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
次回は、7月30日(水)に実施する「首都圏外郭放水路」の「地下神殿」とも呼ばれている巨大な「地下調圧水槽」の見学です。いつもですとこれからHPに案内を掲載して参加者を募るのですが、大江戸だよりの年間スケジュールの中でも注目を集めており、HPでの案内をさせて頂く前にもかかわらず、同好会のLINEグループを通じて既に参加者枠30名が埋まってしまいました。
参加者枠の拡大も検討しましたが、駅と見学施設間の移動手段がコミュニティバスしかないことが判明し、枠の拡大は不可能と判断しました。よって今後参加申込み頂いてもキャンセル待ちになりますので何卒ご了承願います。
【 ハイキング同好会世話役 薮内 滋 記 】
Views: 24
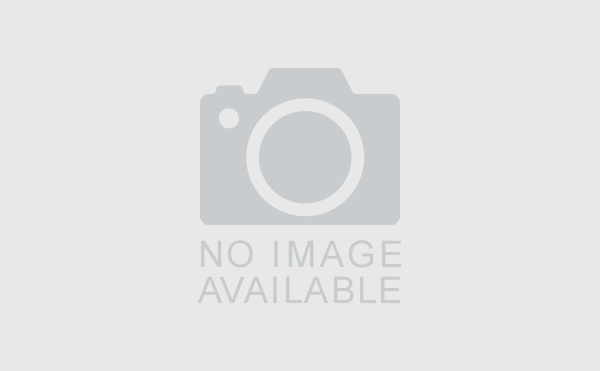
6月に入って,雨も心配でしたが,北鎌倉は,深い緑と爽やかに風に包まれ,修学旅行の時より,一所懸命説明を聞いてました‼️お昼は小町通りにある、歴史のありそうな中華屋さんに,行きました!2階に上がり,小泉元首相や堺正章の写真と女優の亡くなってますが,私の大好きだった,夏目雅子さんの写真があり,ここを訪れた様子でした!
今また,素晴らしい,薮内さんの文章を読んで,振り返ってます!
ありがとうございました♪
又,スケジュールがあった時は,是非参加したいと思ってます
鎌倉散策、興味深く読ませていただきました(^.^)
まだ、ハイキングでの鎌倉参加は、叶ってなくて今回も予定が外せなくて断念してました。
ガイドさんもお二人いらっしゃり詳しく案内されたとか。その場にいたらどれほどたのしかったかなぁ?残念ですが、次回の楽しみに待ちたいと思います。詳しくレポートくださりました、藪内さま。また、細部にわたりお手配などしてくださった中村さま、当日に、参加してないのに、その場に一緒に行ってたような臨場感を楽しめました。有り難うございましたm(__)m
藪内様の事細かな素晴らしい説明文章等を拝見して振り返っているところです。
6月5日天気予報では猛暑、1日中汗だくかと思いきや最初に向かった[浄智寺]では深い緑の木々の中を歩きさわやさな心地良い風が吹いていて癒やされました。亀ヶ谷でも紫陽花を見ながらとても涼しい風にのって難なく歩く事が出来ました!行く先々興味深く皆さんと歩いていて幸せを感じました。昼食は小町通りの]二楽荘]での中華コース全部が美味しく、町田G6名全員満足でした中村様に感謝です。
鎌倉の歴史を再度学ぶは[藪内様の説明文章]にて!とします。
お世話役の藪内様、幹事の皆様有り難うございました。
町田G、野伏澄江
ハイキング同好会 : 北鎌倉~鎌倉散策に参加された皆さま
初夏の北鎌倉散策を閲覧いたしました。
このシリーズで皆出席の方は、全ての鎌倉五山を拝観されたとありますが、昨年のこの時期は「寿福寺」でしたね。境内の紫陽花が有名とか記憶しています。
今回の浄智寺の総門の額「寳所在近(ホウショザイコン)」仏さまの教えや、本堂のご本尊「三世仏」にお参りされ、心豊かになられた事でしょう。
また「布袋尊」のお腹をさすり不老長寿に ! きっと元気で長生きできます。
亀ヶ谷坂切通は急な坂道とありますが皆さま健脚 ! さすがウオーキング同好会ですね。
ハイキング同好会世話役 薮内 滋 様
野伏様のコメントにあるように、鎌倉の歴史を再度学ぶは[藪内様の説明文章]で。
末尾の「冷泉為相(レイゼイタメスケ)の墓」の説明など、平安鎌倉室町と続く時代の流れの一端を、学ばせていただきました。
秋の鎌倉が楽しみです。
石川県支部 中富洋子
石川県支部 中富副委員長様
いつもハイキング同好会の記事をご丁寧にお読み頂き、更に今回は昨年の鎌倉散策の記事まで触れて頂き有難うございます。
コメント頂いています通り鎌倉散策は、いつもガイド協会のガイドさん及び中村烈さん(元ガイド協会メンバー)の歴史や文化まで含めたご案内がすばらしく勉強になりますので、ついつい通常のハイキングの実施報告より詳しく記事に書き込んでしまいます。(記事を読んだ方が、同じコースを記事に目を通しながら散策頂ければと思いつつ)
ところで、石川県支部さんのHPも読ませて頂きました。
まず「百万石踊り流し」の記事ですが、踊りに参加したニッセイ金沢支社が“審査員特別賞”を受賞したとのこと、日本生命の「ニッセイ・サステナプロジェクト」のひとつ“地域連携活動”のお手本となるような活動で感動しました。
また第6回「ふるさと再発見」の記事ですが、“日本銀行新金沢支店と日本生命金沢支社”を見学されたとのことで、個人では中々セッティングの難しい場所だけに参加された23名の会員方が喜ばれている様子が伺われました。
東京都支部の会員の皆様も是非、本部喜楽会HPの石川県支部紹介ページを開いて読んでください。全国支部の紹介ページでも閲覧者数ブッチギリです。
東京都支部事務局 薮内